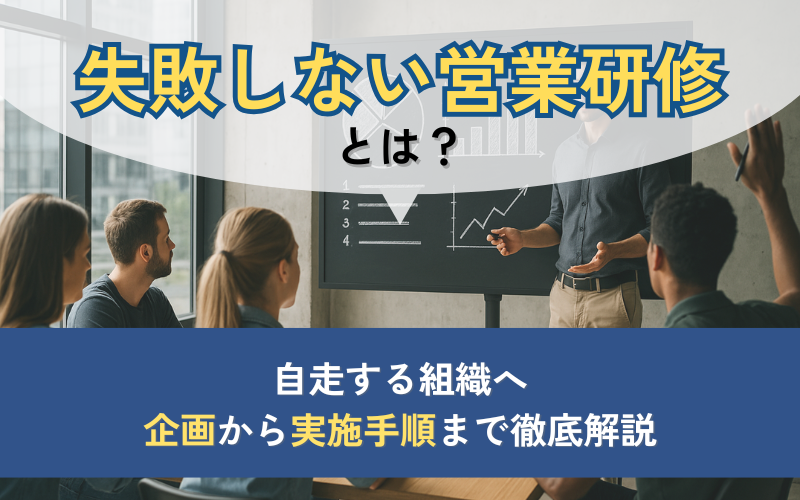営業ノウハウ
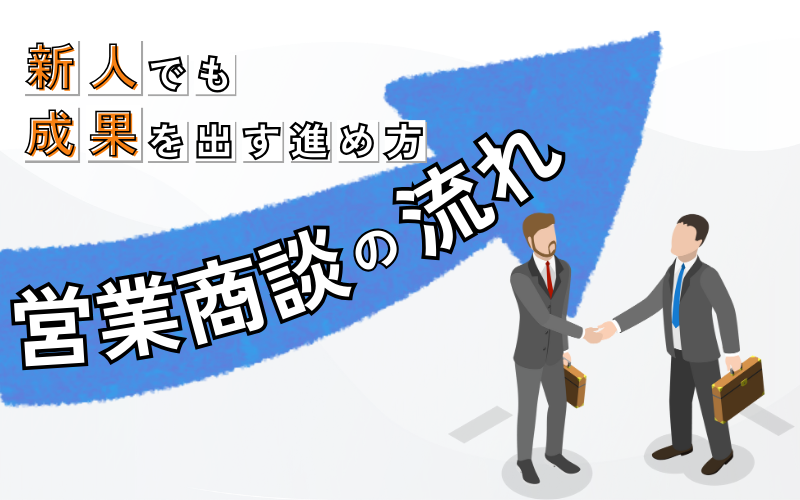
営業職に配属されたばかりの新人社員の中には、「営業での商談の流れがよく分からない」という方もいらっしゃるでしょう。
営業活動における商談には基本的な流れがあります。この流れとは違う進め方をしてしまうと、必要な情報のヒアリングができなかったり、顧客に不信感を与えてしまったりする可能性もあります。結果として、商談での受注率は下がり、売上にも繋がらなくなってしまいます。
今回の記事では、営業商談の具体的な流れと、新人でも成果を出すための商談の進め方について解説していきます。
弊社「CLF PARTNERS株式会社」では、様々な企業の営業活動を支援しており、支援社数350社以上、半年以上の継続率96.5%の実績がございます。 自社の営業活動強化にお悩みの方は、ぜひCLF PARTNERS株式会社までご連絡ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
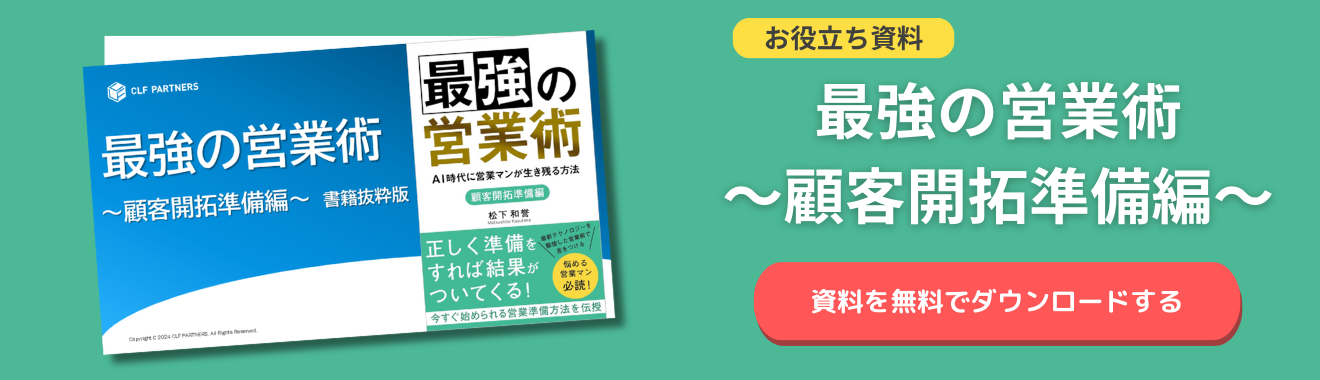
目次
営業で商談を行う目的

まず、具体的な商談の流れを覚える前に、「そもそもなぜ営業活動で商談が必要になるのか」、その目的を理解しておく必要があります。
営業活動で商談を行う目的は、これから紹介する主に3つです。
ビジネス課題のヒアリング
1つ目は、提案先の企業におけるビジネス課題のヒアリングです。
BtoB取引において、基本的に顧客が商品やサービスを購入する理由は、「自社の課題を解決するため」です。
例えば、「売上を上げたい」「業務を効率化して利益率を上げたい」「いい人材を採用したい」といった課題を解決するために、ツールを導入したり、広告を出稿したり、業務を委託したりするのです。
そのため、営業社員は顧客との商談の中でヒアリングを行い、顧客の会社にどのようなビジネス課題があるのかを共に見つけていく必要があります。
提案と擦り合わせ
2つ目は、商品やサービスの提案と擦り合わせです。
商談では、顧客の課題に応じて自社の商品やサービスを組み合わせ、最適な提案が可能です。この「営業が提案を行う」という行為こそが、営業職の付加価値です。
また、提案内容は顧客と擦り合わせながら進めます。不明点を質問し、ニーズに応じて修正を重ねることで、顧客が納得しやすく、提案の検討がスムーズになります。
交渉と合意形成
3つ目は、交渉と合意形成です。
BtoB取引では、一度の契約で大きな金額が動き、多くの関係者が関わることが一般的です。そのため、商品の機能や価格、サービス内容、納期の認識にズレがあると、大きな問題に発展する可能性があります。
営業は商談で認識のズレを防ぐ説明を行い、顧客は金額やサービス面で交渉します。このプロセスを経て合意を形成し、契約を進めることが重要です。
営業商談の流れ
ここからは、実際に営業活動で商談を行う際の流れについて解説いたします。
扱う商材や提案先の事業規模等に関わらず、基本的には同じ流れで商談は進みます。
商談の準備
まず最初に、商談を行うための準備をします。
準備をせずにいきなり商談に挑んでしまうと、商談中に予想外の質問が来た時にうまく対応ができなかったり、顧客の課題に刺さらない浅い提案をしてしまう可能性があります。
商談を行う前には、提案先の企業に対して最低限下記のような情報は把握しておきましょう。
- 業界
- 取り扱う商品やサービス
- 売上高や利益率
- 従業員数
- 支社や支店のある地域
- 競合企業
- 最近のニュース
- 自社への問い合わせ内容(問い合わせがあった場合)
これらの情報は、会社のホームページや採用情報を見るだけでも十分に把握が可能です。
このような情報を整理したうえで、「提案先の企業で想定される課題」「自社の商品やサービスで解決できること」を考え、提案内容として資料にまとめておきましょう。
また、こちらの記事では営業リストの作成代行サービスをまとめて紹介しています。提案先の企業選びに悩んでいる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
※関連記事:営業リスト作成代行サービスおすすめ8選!相場やメリットとデメリットも解説
訪問、もしくはWEB 会議にて商談
次に、アポイントを依頼した日時で相手の企業に訪問、もしくはビデオ会議にて商談を行います。
近年では、訪問をせずにWEB 会議で初回の商談を行うケースも増えてきています。WEB 会議ツールを使う ことで、移動時間を削減し、営業担当の1日の商談回数を増やすことにも繋がります。一方で、対面商談と比べると、顧客と信頼関係を築きにくい側面もあります。
相手企業の希望や商談の目的に合わせて、訪問をするべきかオンラインで商談をするべきかは検討しましょう。
こちらの記事では営業の紹介商談で失敗しないための8つのポイントを紹介しています。商談前にぜひチェックしてみてください。
※関連記事:営業の初回商談の極意|失敗しないための8つのポイントを具体的に解説
挨拶・アイスブレイク
相手の企業に訪問、もしくはWEB会議を開始した後は、まず挨拶を行いましょう。そして、訪問の場合は相手の企業の参加者全員と名刺交換をしていきます。
挨拶や名刺交換が終わった後は、軽くアイスブレイクをするとお互いの緊張感が溶けて商談を行いやすくもなります。アイスブレイクとは、名前の通り「緊張の氷を溶かすようなちょっとした雑談」のことで、オフィスや先方ニュースリリース、事前に調べておいたお会いされる方のパーソナル情報についての話題など商談とは違う話をしていきます。
注意点として、あくまでアイスブレイクは商談に入る前の繋ぎのような役割なので、だらだらと雑談を続けてしまうことは避けましょう。
自己紹介・自社紹介
挨拶やアイスブレイクで場が和んだら、自己紹介と自社紹介を行いましょう。
まず、自分の名前や部署を伝え、自社の事業や商品・サービスを簡単に説明します。ただし、提案はヒアリング後に行うため、初めから売り込むのは控えましょう。
自己紹介が終わったら、相手企業も同様に自己紹介や自社紹介を行います。
課題のヒアリング
自己紹介が終わった後はいよいよ商談です。
まず、提案をする前に相手企業の課題をヒアリングしましょう。
事前に調べた企業情報を基に想定課題を引き出しますが、話を一方的に聞きすぎたり、「いきなり●●といった課題はありませんか?」と直接的に聞くのは避けましょう。
例えば、「弊社には同業界の利益率向上事例があります。」と事例を紹介した上で、「御社でも同様の課題はありますか?」と尋ねるとスムーズです。一言添えて話しやすい雰囲気を作ることが重要です。
課題に対する提案
次にヒアリングした課題を基に自社で解決できる方法を提案します。
まず、「課題を放置するとどうなるか」を共有し、認識を擦り合わせます。例えば、「生産性が低下し利益率が下がる」「競合に新規顧客を奪われる」といった未来を一緒に考えます。
次に、自社のサービスや商品がその課題をどう解決するかを具体的に伝えましょう。具体的な事例や数字のシミュレーションを使うと効果的です。有形商材の場合は実物を見せるのも有効です。
最後に、提案内容の見積もりを提示します。詳細が難しい場合は、概算の費用感を口頭で伝えましょう。ヒアリングした課題を踏まえて、自社でその課題を解決できる方法を提案します。
質疑応答
提案をした後は、提案内容に関して分かりにくい部分や変更して欲しい部分などを相手企業から聞き、提案内容の擦り合わせをしていきます。
例えば、商品の機能面や、サービスの範囲、サポート体制などが質問されやすいです。「提案内容は魅力的なものの、予算がなく値引きができないか」と交渉されることもあるでしょう。
値引きをすれば受注の確度は高くなりますが、利益率が下がり、場合によっては赤字になってしまうことも考えられます。その場での値引き対応はせずに、事前に社内で「どこまでの値引きはOKなのか」、「条件はあるのか」を確認しておくようにしましょう。
その他、もしその場で分からない内容があれば、無理に回答はせずに、一度社内に持ち帰り回答をするようにしましょう。
クロージング
相手企業からの質問に答え、疑問や不安を払拭した後は、契約するかどうかを決めるクロージングを行います。
ここまでの商談で相手企業が自社の提案に興味を持ち、予算感も問題なければ、契約が進んでいきます。
ただ、提案内容を社内ですり合わせたり、他の企業からも話を聞いてみたりするために、契約は後日になるケースも多いです。社長相手の商談であれば当日に契約が決まることもありますが、会社の担当者がその場で自身だけの判断で契約を進めることは難しいはずです。
クロージングの際は無理に契約を進めようとはせず、相手の都合を聞いた上で「いつ頃 契約するかどうかが決まりそうか」を確認するようにしましょう。
アフターフォロー
最後に、商談が終わった後にはアフターフォローを行います。
まず、できれば商談が終わった当日のうちにお礼のメールをお送りします。この際に、商談の議事録や確認事項などもまとめて記載しておくと、認識のずれを防ぐことに繋がります。
また、商談で不足していた情報や、相手が興味を持ちそうな情報があれば、自社の資料やサイトのURLを共有すると良いでしょう。
契約が商談当日に決まらなかった場合は、ヒアリングしておいた検討期間の後、検討状況がどうなったか電話で聞くようにしましょう。
商談で成果を出すためのコツ
ここまで、営業での商談の流れについて具体的に解説をさせていただきました。
新卒の方や営業経験の少ない方は、ヒアリングをせずに提案をしてしまったり、商談後のアフターフォローが抜けていたことが原因で、受注率が下がってしまうことがよくあります。まずはこの基本的な商談の流れをマスターするようにしましょう。
最後に、今回紹介した商談の流れを踏まえて、商談で成果を出すためのコツについて解説します。これらのコツを意識しておくことで、顧客から信頼を得やすくなるでしょう。
商談の目的やゴールを明確にする
まず、商談を行う際は、その目的やゴールを予め明確にしておくようにしましょう。
従来の営業活動では、ただ顧客となる企業に頻繁に通い、相手からの相談を待つような御用聞き営業も珍しくありませんでした。
ですが、インターネットが普及し担当者が自身で情報収集できるようになった昨今では、目的やゴールもなく顧客に会いに行くだけでは売上に繋がりません。
やみくもに商談回数や会う回数を増やすのではなく、商談の方向性や流れを予め想定しておき、ゴールに向かって話を進めていくように意識しておきましょう。
目指す姿や方向性を擦り合わせる
次に、商談では提案先の企業と共に目指す姿や方向性をしっかりと擦り合わせていくことも大切です。
まずは企業の理想の姿を明確にし、その姿と現状とのギャップを把握したうえで、そのギャップを埋めるための提案を行いましょう。この方向性が擦り合わせできておらず、認識にズレがあった場合、どれだけ一生懸命に提案をしても顧客には刺さらず契約はしてもらえません。
事前準備をしっかりと行う
次に、商談を行う前には事前準備をしっかりと行うようにしましょう。
相手の企業に関するリサーチはもちろん、自社での類似実績の把握、商談のトレーニングなど、準備できることは沢山あります。事前準備の量や内容によって商談の質は大きく変わると言っても過言ではありません。
営業担当は忙しいことも多いと思いますが、できる範囲で準備を進めておきましょう。自分1人で全て準備する必要はなく、社内メンバーと協力するのもオススメです。
一方的に話し過ぎない
次に、商談時は一方的に話し過ぎないことも重要です。
「営業職は話すことが仕事だ」というイメージがある方もいらっしゃるかと思いますが、実際の商談では営業が話しすぎると相手にネガティブな印象を与えてしまうリスクがあります。
営業活動における商談は、あくまで顧客の課題を解決するための提案の場です。まずは顧客の事業や課題に関心を持ちながら話を聞き、顧客と擦り合わせをしながらその課題を解決するための提案をするように意識しましょう。
メリットだけでなくデメリットやリスクも伝える
次に、自社の商品やサービスを提案する際は、メリットだけではなくデメリットやリスクも合わせて伝えるようにしましょう。
例えば、「必ず売上が上がります!」「必ず良い人材の採用ができます!」というような導入のメリットばかりを強調するような提案内容は、顧客にとっては逆に怪しくも感じてしまいます。
また、提案内容のメリットばかりを伝え顧客の期待値が上がり過ぎると、実際に契約を行い提案内容を導入した後に期待を下回り、クレームや解約に繋がってしまう可能性もあります。
提案では他の商品やサービスと比較した時のデメリットや、考えられるリスクなども共有したうえで、デメリットを上回るメリットやリスクの回避方法について伝えるようにしましょう。
新人はチームで営業を行う
最後に、新人は1人だけで営業を行うのではなく、上司や他のメンバーも巻き込みチームで営業を行うことをオススメします。
新人は商談経験が少ないため、ヒアリングが不十分であったり、質問に的確に答えられないことがよくあります。貴重なアポイントを無駄にしないためにも特に新人は個人ではなくチームでフォローしながら営業活動をしていくことが大切です。
こちらの記事では組織営業を行う目的や仕組みづくりのポイント等について解説していますので、合わせて参考にしてみてください。
※関連記事:組織営業とは?目的や仕組み作りのポイント、様々な企業の成功事例を解説
まとめ
今回の記事では、営業活動における商談の具体的な流れと、新人でも成果を出すための進め方について解説いたしました。
新人の営業社員の方は、まずは商談の流れをマスターし、自然な形で顧客へのヒアリングや提案を行えるようにトレーニングや実践を繰り返し行っていきましょう。
また、今回紹介した「商談で成果を出すためのコツ」の中で自身ができていない部分があれば、ぜひこの機会に取り入れてみてください。
弊社CLF PARTNERS株式会社では、様々な企業への営業支援を行っており、支援社数350社以上、半年以上の継続率96.5%の実績がございます。
また、営業コンサルで培われたノウハウを生かした営業組織のスキルトレーニングや新人向け教育も行っております。
「新人の商談での受注率が低い」「組織やチームでの営業活動ができていない」といった課題を解決するコンサルティングや研修を提供いたします。
超実践型研修も行っており、研修後は現場での伴走支援までお任せいただけます。
自社の営業活動強化にお悩みの方は、ぜひCLF PARTNERS株式会社までご連絡ください。 皆様のビジネスの成長を全力でサポートいたします。
この記事の監修者
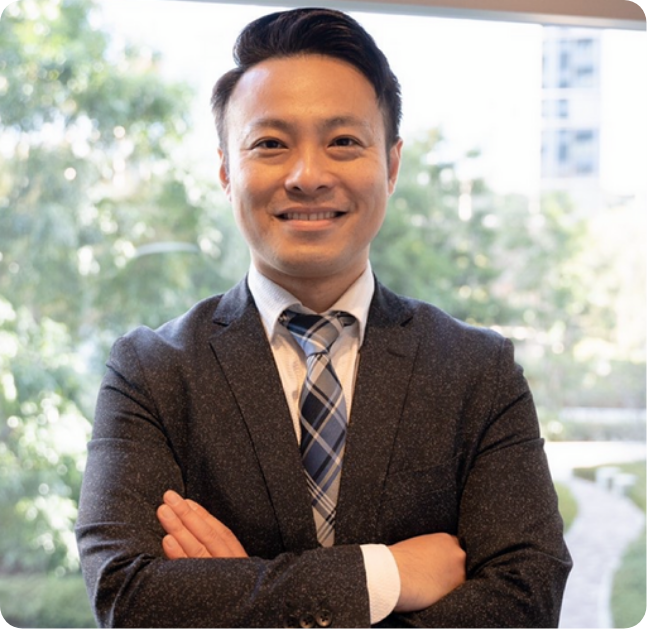
CLF PARTNERS株式会社
代表取締役社長 松下 和誉
大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事
公式Xアカウント:https://x.com/clf_km