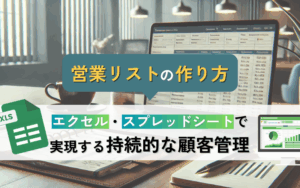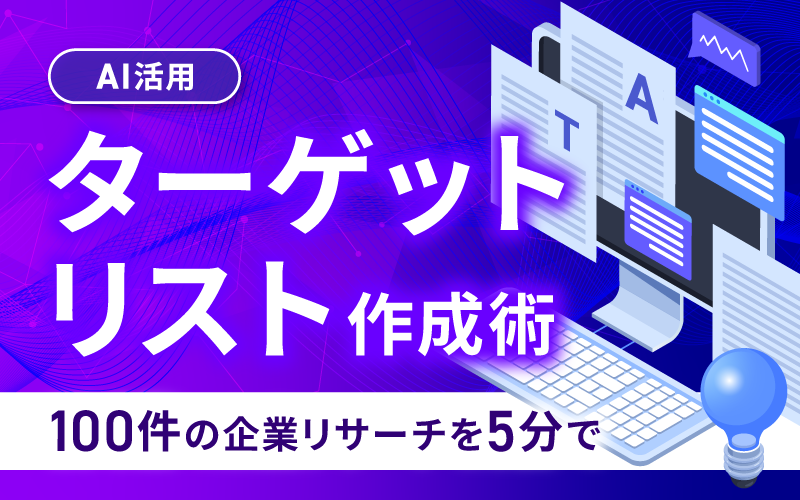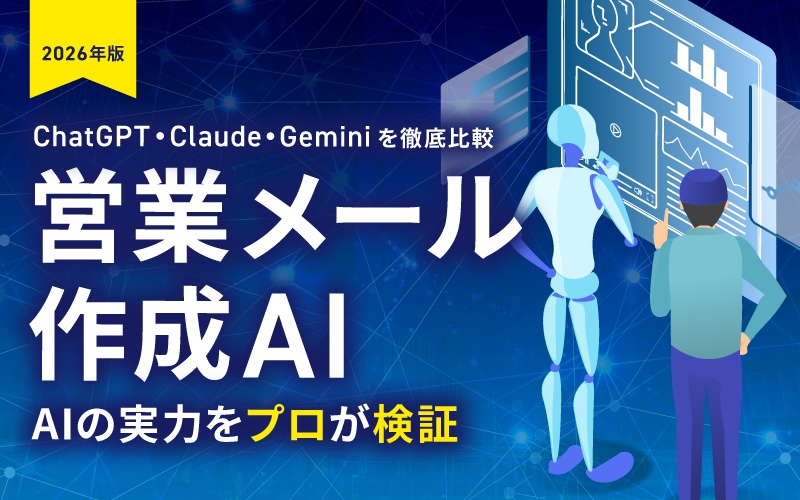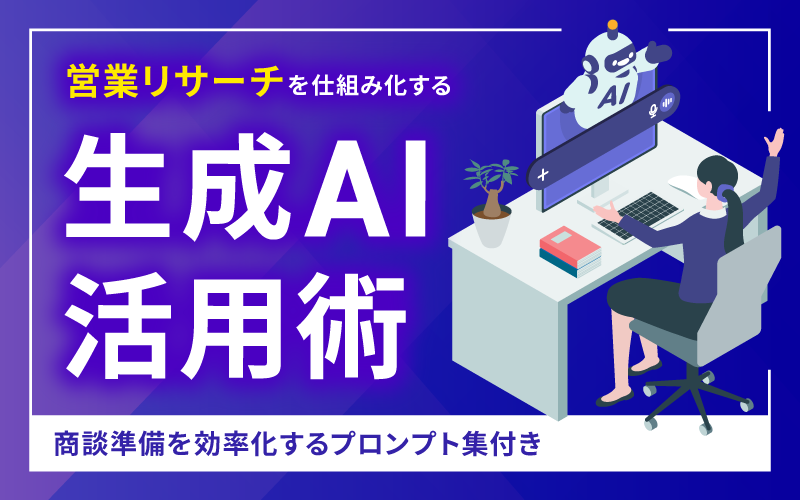営業戦略

営業戦略の立案に悩み、適切なターゲット選定ができずに苦労している方も多いのではないでしょうか。「どの顧客層にアプローチすべきか分からない」「リソースが限られる中で効率的に成果を出せない」など、様々な課題に直面することがあるでしょう。
本記事では、そんな悩みを解決するための「営業戦略におけるターゲット選定の方法」について詳しく解説します。成功事例も交えながら、具体的な選定プロセスやフレームワークの活用法をご紹介します。
当社CLF PARTNERSは、これまでに350社以上を支援し、半年以上の継続率96.5%の実績を持つ営業のプロフェッショナル集団です。ターゲット選定や営業戦略の立案にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
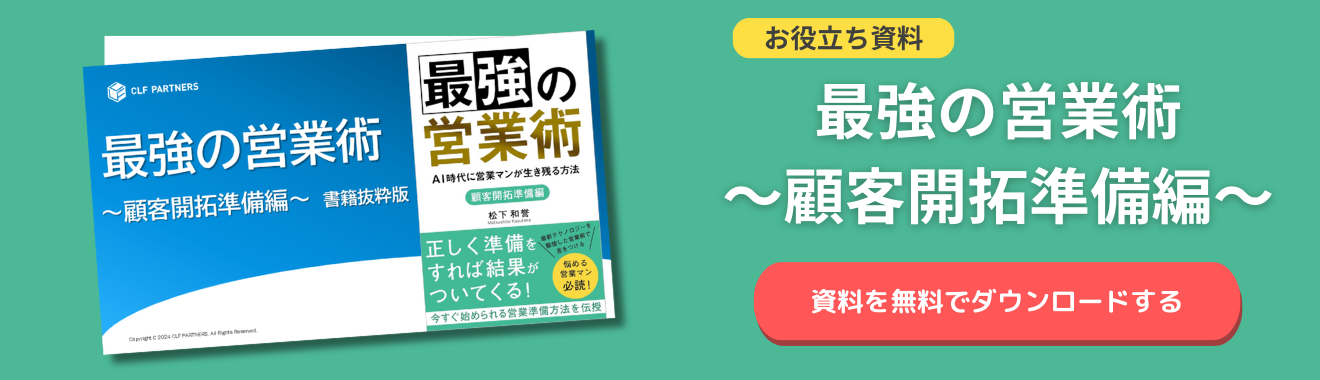
目次
営業戦略におけるターゲットとは
営業戦略におけるターゲットとは、企業が提供する商品やサービスの最適な顧客層のことです。ターゲットを明確にし、限られた経営資源を効率的に活用することで、最大の成果を得られます。
例えば、法人向けセキュリティソフトウェアを提供するBtoB企業なら、データ保護に課題を抱える金融機関や、情報漏洩リスクの高い医療機関がターゲットになるでしょう。
ターゲットを絞り込むことで、顧客のニーズに合わせた的確なメッセージを作成でき、営業活動の効率も向上します。さらに、商品開発やカスタマーサポートなどでも顧客ニーズに沿った戦略を立てやすくなります。
ペルソナとの違い
ターゲットとペルソナは、似て非なるものです。ターゲットは顧客層全体を指し、ペルソナはその中の具体的な個人像を表現します。
例えば、ターゲットが「中小企業のIT担当者」なら、ペルソナは「従業員100人の製造業で働く35歳の男性システム管理者、山田さん」といった具合です。
ペルソナを作成することで、顧客の日常や課題、ニーズをより深く理解できるようになります。ターゲット層全体の傾向を把握しつつ、個々の顧客に寄り添ったアプローチが可能になるのがメリットです。
営業戦略でターゲット選定が重要な理由
ターゲット選定は、営業戦略で成果を出すには欠かせない要素です。ターゲットを絞り込むと市場での競争力を高められます。特定の顧客層に焦点を絞ることで、そのニーズに合わせた独自のサービスを提供できるからです。
例えば、環境に配慮した商品を求める若い世代をターゲットにすれば、エコ素材を使った商品開発や、環境保護活動と連携したマーケティングなどの戦略を立てられます。競合他社との違いを明確に示し、市場での強みを発揮しやすくなります。
また、ターゲットを絞ることで、広告や販促活動を最適化することが可能です。全ての人に向けて幅広く宣伝するのではなく、ターゲット層が多く利用するメディアや場所に集中して宣伝することで、限られた予算でも高い効果を得られるでしょう。
営業戦略におけるターゲット選定のやり方8ステップ

ターゲット選定は以下の8ステップで行いましょう。
- 市場調査を行う
- 顧客をセグメンテーションする
- ターゲット市場を決める
- ペルソナを設計する
- 商品・サービスの提供価値を見直す
- ターゲット企業をリストアップする
- 施策を実行する
- 効果を検証する
順番に解説します。
1.市場調査を行う
まずは市場全体を把握しましょう。例えば、製造業の会社なら、産業別の業界動向や、IoTやAIなどのデジタル技術の導入状況を調べます。業界団体の統計やアンケート調査などで情報収集するのがおすすめです。
Web上のデータ分析ツールを使って、検索キーワードのトレンドを見るのも効果的です。また、既存顧客にインタビューして、生の声を聞くのも良いでしょう。
こうした調査により、市場の大きさや成長の見込み、顧客のニーズや課題が見えてきます。
2.顧客をセグメントする
次に、調査結果をもとに顧客を分類します。BtoBにおけるセグメンテーションでは、以下のような切り口を効果的に組み合わせることが重要です。
- 企業特性:業界、業種、従業員数、売上高、資金調達額、設立年数、所在地など
- ビジネスモデル・商流:事業会社、代理店など、ビジネスモデルや商流に基づく分類
- 部署・職種:情報システム部、人事部、経理部など、製品・サービスを利用する部署や職種
- 役職・決裁権:利用者・購買意思決定者の役職や決裁権限の範囲
セグメンテーションの際は、単に「従業員50人以下の中小企業」や「年商10億円以上のIT企業」といった自社都合の分類にとどまらず、「買う理由(ニーズ)が発生する企業群」を特定することを目指しましょう。
また、定量的な企業データだけでなく、以下のような質的な要素も考慮することで、より精緻なセグメンテーションが可能になります。
- 価値観:コスト重視、品質重視、環境配慮、イノベーション志向 など
- 行動特性:デジタル化に積極的、従来型のやり方を好む、意思決定サイクルの長さ など
このような多角的なセグメンテーションにより、各グループの特徴や購買意思決定プロセスがより明確になり、効果的なマーケティング戦略やアプローチ方法を設計しやすくなります。
3.ターゲット市場を決める
セグメントした顧客グループの中から、自社にとって最も魅力的でアプローチしやすい市場を選定します。その際、狙える市場規模を正確に把握することが重要です。
例えば、「従業員100〜500人規模でデジタル化に積極的な製造業」といった大まかな定義ではなく、「100~500名規模でデジタル投資に積極的な自動車部品メーカーや半導体製造装置メーカーのDX推進部マネージャー」といった具体的なターゲット設定が求められます。
このレベルまで明確化することで、ターゲットの本質的な課題やニーズ、行動特性を深く理解できます。「女性向け」や「20代~50代の経営者」といった広すぎる定義では、明確なインサイトを得にくく、選ばれる理由も生まれにくくなります。
市場理解の第一歩は、ターゲットのインサイトを深く掘り下げ、その層がどれくらい存在するのかを定量的に把握することです。ターゲット市場を決める際には、以下の点を考慮します。
- 市場規模は十分か
- 競合は多すぎないか
- 自社の商品・サービスで差別化できるか
- ターゲットが明確な購買ニーズを持っているか
- 自社の強みがターゲットに響くか
具体的なターゲットを定義することで、経営資源を最も効果的に投入できる市場を特定し、マーケティングの成功確率を高めることができます。
4.ペルソナを設計する
ターゲット市場が決まったら、次のステップとしてペルソナを設計します。ペルソナとは、理想的な顧客像を具体的に表現した架空の人物のことです。単なる抽象的な顧客層ではなく、一人の人間として詳細に描写することが重要になります。
例えば、「40代後半の男性。製造業の中堅企業で情報システム部長を務める。業務効率化とコスト削減が課題で、新しい技術には興味があるが導入には慎重。前職はSIer勤務で、ベンダーの視点も理解している。経営層からDX推進を任されているものの、現場との温度差に悩んでいる」といった具体的な設定が望ましいでしょう。
効果的なペルソナ設計には、以下の要素を含めると営業活動に役立ちます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基本属性 | 年齢、性別、家族構成、居住地など |
| 業務内容 | 役職、意思決定権の範囲、日常業務、部下の人数 |
| 業務課題 | 直面している問題、プレッシャーの要因、評価指標 |
| キャリア背景 | 前職、業界経験年数、専門知識の深さ |
| 価値観 | リスク許容度、新技術への姿勢、重視するポイント(コスト・品質・スピード) |
| 情報収集習慣 | よく読む業界誌、参加する展示会、信頼する情報源 |
ペルソナを具体的に設定することで、営業担当者は「誰に」「何を」「どのように」提案すべきかを明確にイメージできます。これにより、単なる商品説明ではなく、相手の課題や価値観に響く提案が可能になります。
5.商品・サービスの提供価値を見直す
ターゲット市場とペルソナが決まったら、自社の商品やサービスがどのように顧客の課題を解決できるか、改めて検討しましょう。
例えば、製造業向けの生産管理システムを提供している場合、中小企業と大企業では抱える課題が異なります。中小企業なら導入コストや使いやすさが重要かもしれません。一方、大企業ならグローバル対応や他システムとの連携が重要かもしれません。
自社の強みを活かしつつ、顧客に合わせた価値提案ができるよう、商品やサービスの特徴や訴求ポイントを調整します。場合によっては、新たな機能の追加や、不要な機能の削除も検討しましょう。
6.ターゲット企業をリストアップする
ペルソナに基づいて、具体的な営業先となる企業をリストアップします。業界団体の会員リストや、企業情報データベース、展示会の出展者リストなどを活用するのがおすすめです。
その際、企業規模や業種、所在地などの基本情報だけでなく、可能な限り意思決定者の情報も集めます。また、WebサイトやSNSの投稿から、その企業の最近の動向や課題なども調べておくと良いでしょう。こうして作成したリストを、営業部門で共有し、優先度をつけて効率的にアプローチしていきます。
7.施策を実行する
ターゲットが決まったら、営業活動を開始します。ターゲット企業のリストを基に、DMを送ったり、架電したりしてアプローチしましょう。
また、営業担当者が直接訪問する際も、事前に収集した情報を基に、相手のニーズに合わせたトークスクリプトを準備します。これらの活動を通じて、見込み客との接点を増やし、商談の機会を作っていきます。
8.効果を検証する
最後に、実施した施策の効果を検証します。例えば、メール配信なら開封率やクリック率、セミナーなら参加者数や商談につながった件数を測定します。これらの数値を、事前に設定した目標値と比較し、達成度を評価しましょう。
単なる数字だけでなく、質的な面も検証することが重要です。例えば、営業担当者からのフィードバックを集め、ターゲット層の反応や商談の質がどうだったかを分析します。顧客からの意見やクレームなども貴重な情報源となります。
検証結果をもとに、ターゲット選定が適切だったか、アプローチ方法に改善の余地はないかを考察しましょう。
営業戦略でターゲット選定に役立つフレームワーク
ターゲット選定を効果的に行うため、以下の3つのフレームワークが広く活用されています。
- STP分析
- 6R
- プロファイリング
それぞれの特徴と使い方を見ていきましょう。
なお、営業戦略で使えるフレームワークについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
STP分析
STP分析とは、以下の3つのステップの頭文字を取った、マーケティングの代表的なフレームワークです。
- Segmentation
- Targeting
- Positioning
このフレームワークを使うことで、市場全体を細分化し、最も魅力的なセグメントを特定し、そこでの自社の位置づけを明確にできます。
例えば、法人向けセキュリティソフトウェアを提供するBtoB企業の場合、以下のように活用できます。
Segmentation:顧客を業種(金融、医療、小売など)や企業規模(大企業、中小企業)で分類
Targeting:「中小規模の医療機関」にターゲットを絞る
Positioning:「医療データの保護に特化した、導入が簡単で信頼性の高いセキュリティソリューション企業」として自社を位置づける
STP分析を通じて、限られた経営資源を最も効果的に活用し、競争優位性を築けます。
6R
6Rとは、ターゲット選定時に考慮すべき6つの重要なポイントを示すフレームワークです。具体的には以下の6つの要素から構成されています。
- Realistic Scale(市場規模)
- Rival(競合の強さ)
- Rate of Growth(市場の成長性)
- Rank(顧客の優先順位)
- Reach(アプローチの到達可能性)
- Response(アプローチ効果の測定可能性)
6Rを活用することで、ターゲット選定時に見落としがちな重要な点を押さえられます。市場規模だけでなく、競合状況や成長性、アプローチのしやすさなど、様々な角度からターゲットを評価できるのです。
例えば、大きな市場でも競合が激しければ参入が難しいかもしれません。逆に、小さくても成長性の高い市場なら、将来性があるかもしれません。6Rを使うことで、より戦略的で持続可能なターゲット選定が可能になります。
プロファイリング
プロファイリングとは、ターゲットとなる顧客や企業の特性を詳細に分析し、理解を深める手法です。
以下はプロファイリングの一例です。
- 従業員50人規模の金属加工会社の社長
- デジタル化による生産性向上に関心がある
- 業界誌や展示会から情報を得ている
- 人手不足が課題で、自動化設備の導入を検討中
プロファイリングを基に、業界誌に広告を掲載したり、展示会でデモを実施したりと、ターゲットに響くマーケティング戦略を実施できます。
BtoB企業が営業戦略のターゲット選定を行う際の注意点
BtoB企業がターゲット選定する際、以下の2点に特に注意を払う必要があります。
- 利用者と決裁者が異なる
- 年齢・性別だけで絞り込まない
それぞれ詳しく解説します。
利用者と決裁者が異なる
BtoB企業がターゲット選定を行う際、利用者と決裁者が異なる点に注意が必要です。例えば、社内システムの導入を考える場合、実際に使うのは現場の従業員でしょう。しかし、購入を決めるのは経営層や情報システム部門の管理職である可能性が高いです。
このため、両者のニーズや判断基準を理解し、それぞれに合わせたアプローチが求められます。利用者には、使いやすさや業務効率化のメリットを訴求するのが効果的です。決裁者には、コストの削減効果や競争力の向上といった経営的視点からの価値を訴求するなど、ターゲットに応じてアプローチを変える必要があります。
年齢・性別だけで絞り込まない
BtoB市場では、年齢や性別だけでターゲットを絞り込むのは適切ではありません。例えば、「40代の男性」というだけでは、その人が大企業の役員なのか、中小企業の経営者なのか、はたまた現場の管理職なのかがわかりません。
それぞれ抱える課題や決定権限が異なるため、アプローチ方法も変わってきます。代わりに、企業規模や業種、役職、抱える経営課題などでセグメントを細かく分けることが重要です。
「従業員100人規模の製造業で、生産性向上に課題を感じている工場長」といった具合に、より具体的に定義することで、アプローチの制度を高められるでしょう。
営業戦略のターゲット選定の成功事例

ターゲット選定は企業の成功に不可欠な要素です。以下の3つの事例は、それぞれ独自の方法でターゲットを絞り込み、新しい市場を開拓することに成功しています。
- 株式会社富士産業
- ベルフェイス
- kubell(旧Chatwork)
富士産業
非鉄金属鋼材の販売を主業務とする富士産業は、価格競争に陥りがちな業界で新たな成長戦略を模索していました。売上の9割以上を占める鋼材販売ではなく、新規事業である製作金物に着目し、ターゲットを設計・デザイン事務所に絞り込んだのです。
Webサイトも「一般の人が問い合わせしやすいこと」をコンセプトに、かっこよさより親しみやすさを重視。競合が多い「加工」に関するキーワードではなく、製作金物に特化したキーワードでSEO対策を行いました。
この明確なターゲット選定と差別化戦略により、リニューアル後は月数件だった問い合わせが数十件に増加。公開からわずか2ヶ月で制作費を回収し、製作金物の受注増加が本業の鋼材販売にも好影響を与える好循環を生み出しました。
ベルフェイス
ベルフェイスは、オンライン商談システム「bellFace」を提供するSaaS企業です。同社は、コロナ禍での苦境を乗り越え、金融業界向けオンライン商談ツールとして成功を収めています。
当初は幅広い業界をターゲットにしていましたが、Web会議ツールの台頭により苦戦。金融業界の顧客からの声を丁寧に聞き、そのニーズに特化したサービスへとピボットしました。
具体的には、オンラインで契約を完結できる機能などを搭載した、金融業界のリテール営業に特化した製品にアップデート。競合のWeb会議ツールでは解決できない課題に応え、金融×リテール営業市場で高いシェアを獲得するに至りました。
kubell(旧Chatwork)
kubell(旧Chatwork)は、ビジネスチャットツール「Chatwork」を提供するSaaS企業です。当初は幅広い顧客層をターゲットにしていましたが、SMB(中小企業)に焦点を絞って成功を収めています。
具体的には、中小企業のニーズに合わせて、シンプルで使いやすいUIを維持しつつ、セキュリティ面でも優れた機能を提供。さらに、PLG(Product-Led Growth)戦略を採用し、ユーザー同士の紹介で自然と広がるネットワーク効果を活用しました。
この戦略転換により、競合の大手企業と差別化し、中小企業向けビジネスチャット市場で高いシェアを獲得。顧客基盤を活かしたアプリ構想など、さらなる成長戦略も描いています。
まとめ|営業戦略の成功はターゲット選定が鍵を握る
本記事では、営業戦略におけるターゲット選定の重要性と方法、成功事例を解説しました。適切なターゲット選定は、限られた経営資源を効率的に活用し、最大の成果を得るための鍵となります。
なお、ターゲット選定と戦略立案には専門知識が必要です。CLF PARTNERSは350社以上の支援実績を持つ営業のプロフェッショナル集団として、皆さまの課題解決をサポートします。ターゲット選定や営業戦略の改善にお悩みの方は、ぜひCLF PARTNERSにご相談ください。
この記事の監修者
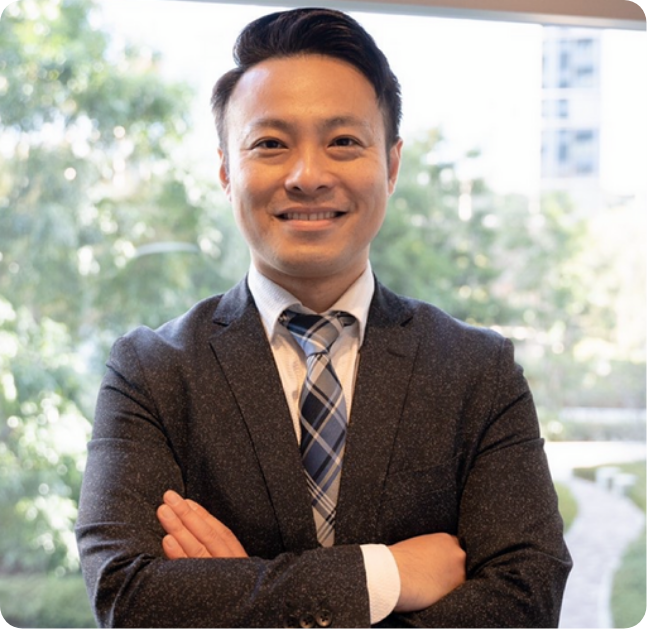
CLF PARTNERS株式会社
代表取締役社長 松下 和誉
大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事
公式Xアカウント:https://x.com/clf_km