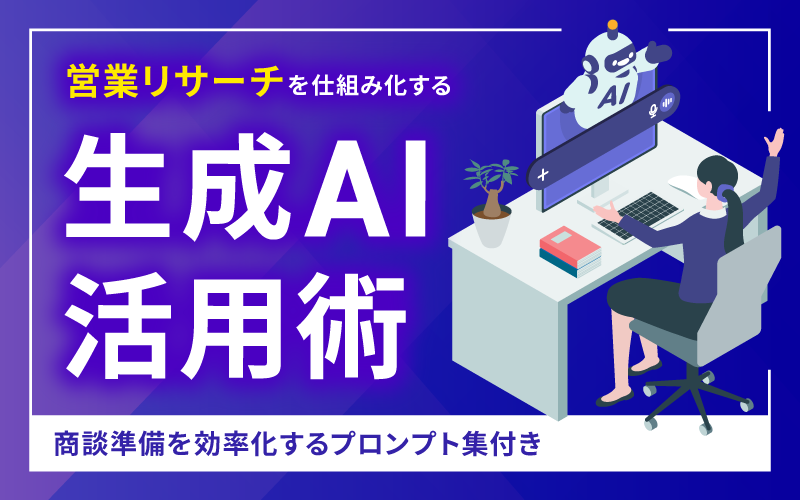営業戦略

「期初や四半期ごとの目標設定時に、どのように営業目標を立てればよいのか分からない」
「トップダウンで決まった数値目標に現場が納得しておらず、モチベーションが上がらない」
このような悩みを抱える営業責任者は少なくありません。
BtoB営業に携わる多くの業界で、特に新規開拓が重要な企業においては、効果的な営業目標の設定が必要です。適切な目標設定なくして、営業戦略を機能させ、営業活動の成果を最大化することは困難です。
本記事では、営業目標の決め方から達成までのプロセスを、フレームワークや具体例を交えて解説します。
また、弊社「CLF PARTNERS株式会社」では、幅広い業界の企業に対して、支援社数350社以上、半年以上の継続率96.5%という実績を持つ営業支援サービスを提供しています。
営業組織における目標設定から達成までの一貫した支援を、営業コンサルティングと営業研修の両面から行っています。
本記事の内容を参考に自社の営業目標設定を見直す際、専門家のサポートが必要と感じた場合は、ぜひお気軽にご相談ください。現在、月5社限定で営業組織の課題診断+改善策提案(60分無料) も実施しています。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
⇒ 【無料】営業組織の課題と対策を壁打ちしてもらう
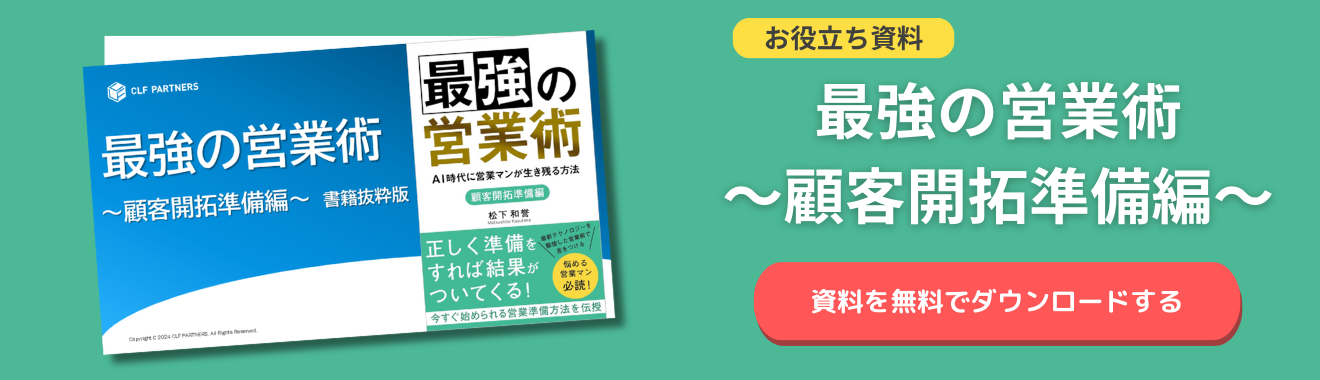
目次
営業目標が組織の成果を左右する理由
営業目標は、単なる「数値管理」ではなく、組織全体の意思決定・行動・育成を方向づける軸になります。
適切に設計された目標は戦略の実行精度を高め、現場の迷いを減らし、成果創出の再現性を強化します。そのため、まずはなぜ営業目標が重要なのかを分解して理解する必要があります。
営業目標は戦略と直結しているため
営業目標は、戦略を現場に落とし込むための起点です。曖昧な目標では、戦略そのものが機能しません。
ある調査では、営業パーソンの半数が前年度の目標を達成できておらず、その理由として最多だったのが「営業戦略の不備」(31%)でした。これは、目標と戦略の質が成果に直結することを示しています。
例えば、「売上5,000万円」という目標だけでは、誰に、何を、いつ売るのかが見えてきません。一方で、「新規顧客10社から平均500万円を受注」と設定すれば、戦略の方向性が具体化され、実行に移しやすくなります。
このように、営業目標は戦略の土台であり、その設定の精度が組織の成果を左右するのです。
参考:PR TIMES
現場の行動を左右する優先順位が明確になる
営業目標を設定することで、現場の行動における優先順位が明確になります。限られた時間とリソースの中で、何に注力すべきかを判断しやすくなり、全ての営業活動が目標達成に向けて整っていくからです。
実際、継続的に成果を上げている営業パーソンは、未達者の約2倍の頻度で戦略を立て、内省の時間を確保していることが分かっています。
具体的には、以下のような行動が習慣化されています。
- 期初に顧客を分類し、優先順位と戦術を設定
- 日々のPDCAと内省を継続
- 商談前に顧客情報を収集し、仮説を立てて臨む
このように、目標は行動の指針となり、最も効果的な取り組みに集中できる環境をつくります。その結果、組織全体の生産性と成果が飛躍的に高まるのです。
参考:PR TIMES
評価と育成の基準が揃い、組織の再現性が高まる
明確な営業目標は、評価と育成の基準をそろえ、組織全体の成果を再現可能にします。 目標が曖昧だと、評価も育成も属人化し、成果の再現が難しくなります。
調査では、目標を達成している企業の43.0%が「人材育成の仕組みがある」と回答。一方、未達企業では25.7%にとどまり、約1.7倍の差が見られました。
例えば、「新規10社の受注」という明確な目標があることで、必要なスキルも見えてきます。
- リスト作成力
- 初回商談の設計力
- クロージング力
これらを評価項目に反映させれば、強化すべきポイントが明確になり、育成も体系的に進められます。
このように、営業目標は評価と育成を整える基盤となり、組織全体で成果を再現する仕組みを築けるのです。
参考:PR TIMES
営業目標の決め方|ゴールから逆算する4STEP
営業目標は場当たり的に決めるのではなく、必ず「事業目標→KPI→行動」の順で逆算して設計することが重要です。論理的な分解を行うことで、達成までの道筋が可視化され、メンバー全員が迷わず動ける状態をつくれます。
ここからは具体的な4ステップを見ていきましょう。
STEP1:事業目標(KGI)を営業チームにブレイクダウンする
営業目標の設定は、まず事業全体のゴール(KGI)を営業チームの責任範囲に落とし込むことから始まります。この段階で、全社目標と営業目標の接続が曖昧だと、以降の施策がすべて的外れになりかねません。
KGIと営業目標を切り離さず一貫して設計することで、営業活動が経営戦略と直結し、組織全体の方向性が揃います。
例えば、事業目標が「年間売上5億円」であれば、マーケティングやカスタマーサクセスの貢献分を除き、営業チームの責任範囲を「新規3億円+既存2億円」と明確に定義します。さらに四半期・月次単位に分解し、「Q1は新規7,500万円」といった具体的な目標へと落とし込みます。
こうして、KGIを営業チームの責任に応じて正確にブレイクダウンすることが、次のKPI設計の土台となります。
STEP2:KGIから必要なKPIを分解して、達成の公式を作る
KGIが明確になったら、それを実現するためのKPIを分解し、「達成の公式」を構築します。この公式があることで、どの指標をどれだけ改善すればKGIに到達できるかが可視化され、戦略的な判断が可能になります。
具体的には、「新規売上3億円」を達成するために、以下のように指標を分解します。
- 平均受注単価:300万円
- 必要受注件数:100件
- 商談化率:20% → 必要商談数:500件
- アポ率:30% → 必要架電数:1,667件
このようにKPIを要素ごとに分解することで、「商談化率を25%に上げられれば、必要な商談数は400件に減る」といった具体的な戦略立案が可能になります。
STEP3:KPIをメンバーの行動目標に落とし込む
設定したKPIを、現場で実行可能な行動目標にまで具体化します。数値だけでは現場は動けないため、「誰が・何を・いつまでに」というレベルで明確にすることが重要です。
例えば、「月間商談数50件」というKPIに対しては、以下のような行動目標が考えられます。
- 毎日10件の新規架電を実施
- 週2回、既存顧客へのフォローアップメールを送信
- 週1回、商談内容の振り返りとトークスクリプトの改善を実施
こうした行動目標があれば、メンバーは日々やるべきことを迷わず判断でき、進捗管理もしやすくなります。
STEP4:個人のスキル・担当領域に合わせて最終調整する
最後に、メンバー個々のスキルレベルや担当エリアに応じて目標を調整します。全員に一律の目標を課すと、現実とかけ離れた目標となり、モチベーションの低下や未達成の常態化を招く恐れがあります。
例えば、新人には「月間アポ獲得10件」、中堅には「月間受注2件」、ベテランには「大型案件1件+後輩育成2名」といったように調整を行います。また、担当市場の規模や既存顧客の有無に応じて補正し、公平性を確保します。
このように、個人の特性を踏まえた目標設定を行うことで、全員が納得感を持って取り組める体制を整えることができます。
営業目標の精度を高める3つのフレームワーク
営業目標の精度を高めるには、属人的な判断ではなく、普遍的に使えるフレームワークを活用するのが効果的です。SMART・MUST/WILL/CAN・OKRなどは、目標を「明確・達成可能・再現性ある形」に変換しやすく、組織の方向性を揃える力があります。
代表的な3つを順に見ていきましょう。
SMARTの法則:達成可能で再現性の高い目標をつくる基本フレーム
SMARTの法則は、目標を具体的かつ実行可能な形に落とし込むための、基本かつ有効なフレームワークです。曖昧な目標設定による未達を防ぎ、組織全体で再現性のある成果を生み出す基盤となります。
SMARTは、要素は以下の通りです。
- Specific(具体性):誰が見ても理解できる明確な目標であること
- Measurable(測定可能性):数値などで進捗を確認できること
- Achievable(達成可能性):努力すれば到達可能な現実的な目標であること
- Relevant(関連性):組織の方針やビジネスの目的と整合していること
- Time-bound(期限が明確):いつまでに達成するか、期限が設定されていること
例えば、「新規顧客を増やす」という漠然とした目標を、「3ヶ月以内に新規法人顧客15社と契約を締結する」と設定すれば、行動計画が立てやすく、進捗の確認や改善もスムーズになります。
MUST・WILL・CANモデル:個人目標を最適化する才能マネジメントフレーム
MUST・WILL・CANモデルは、組織の期待と個人の意欲・能力をつなげ、納得度の高い目標を設定するためのフレームワークです。3つの要素が重なるポイントに目標を置くことで、やる気と実行力を両立できます。
構成要素は以下の3つです。
- MUST(組織からの期待):会社やチームが求める役割・責任
- WILL(本人のやりたいこと):実現したいキャリアや目指す姿
- CAN(本人のできること):持っているスキルや得意な領域
例えば、新規開拓が得意な営業に「既存顧客の深耕」を任せても力を発揮しづらいかもしれません。しかし、「新規法人10社の開拓」といった目標であれば、本人の強み(CAN)と意欲(WILL)、そして組織のニーズ(MUST)が一致し、高い成果につながります。
OKR:組織の方向性を揃え、チャレンジングな目標を機能させる仕組み
OKRは、企業・部門・個人の目標を階層的に連動させることで、組織全体のベクトルを揃えつつ、挑戦的な目標の達成を促すフレームワークです。
Googleやメルカリをはじめとする成長企業が導入し、高い成果を上げていることでも注目されています。
OKRは以下の2つの要素で構成されます。
- Objectives(目標):3ヶ月程度で達成を目指す、定性的かつインパクトのある目標を1つ設定
- Key Results(成果指標):目標達成を評価するための定量指標を3〜5個設定
最大の特徴は、「達成率60〜70%を想定した挑戦的な目標設定」です。例えば、「新規顧客開拓で業界トップクラスの営業組織になる」という企業全体のObjectiveに対し、部門では「新規商談数を前年比150%達成」、個人では「新規法人15社と契約を締結」といったKey Resultsを設定します。
このように、すべてのOKRが組織内で共有されることで、個人レベルでも自らの業務が会社目標にどう貢献しているかを理解でき、一体感と挑戦意欲を高めることが可能です。
【レベル別】営業目標設定の具体例
営業の成長段階に応じて、目標の設計思想は大きく変わります。新人は行動量の確保、中堅は成果と行動のバランス、ベテランはチーム貢献や難易度の高い案件が中心になります。レベルに合わせて何を求めるべきか、具体的なKPI・行動例とともに確認していきましょう。
新人営業の目標例(行動目標中心)
新人営業においては、売上数値よりもコントロール可能な「行動量」を最優先指標として設定します。
まだスキルや顧客基盤が未熟な段階で成果のみを求めると、何をすべきか迷走し、モチベーション低下を招くリスクがあるためです。まずは「やれば達成できる目標」を通じて成功体験を積み、正しい営業習慣を定着させることが将来の成果への近道となります。
▼KPI例
- 1日30件の新規架電
- 週2回の上司ロープレ実施
- 商談同席後の議事録提出(当日中)
▼行動例
- 毎朝8:50に架電リストの優先順位付けを行い、迷う時間をなくす
- ロープレで指摘された改善点をノートにまとめ、翌日の架電前に復唱する
- 商談の録音を聞き直し、顧客の質問に対する自分の回答の間(ま)をチェックする
新人の段階では徹底して行動を管理し、「成果を出すための型」を身体に染み込ませることが組織としての最適解となります。
中堅営業の目標例(成果と行動のバランス)
ある程度業務に慣れた中堅営業には、「成果(売上)」とそこに至る「プロセス(質)」の双方をバランスよく求めます。
行動量だけで成果が伸びるフェーズを過ぎ、成約率や案件単価といった「質の改善」が業績向上の鍵となるためです。単なる訪問数ではなく、受注確度を高めるための戦略的な動きができているかを評価する必要があります。
▼KPI例
- 商談からの案件化率30%
- 月間提案数15件
- キーマンとの面談実施数
▼行動例
- 商談前に必ず顧客のIR情報や業界ニュースを調べ、仮説を立ててから訪問する
- 失注した案件について、「価格」「機能」「時期」以外の真因を分析しレポート化する
- 既存顧客に対し、他部署の課題ヒアリングを意図的に行いクロスセルの種を探す
中堅層には思考を伴う目標を設定し、自律的にPDCAを回して勝率を高められる人材へと進化させることが重要です。
ベテラン営業の目標例(チーム貢献や高難易度案件)
ベテラン営業には、個人の数値達成に加えて「組織への貢献」や「高難易度案件の攻略」を目標の中核に据えます。
単に売上を上げるだけでなく、彼らの持つノウハウを組織に還元し、チーム全体の底上げを図ることが会社としての最大の利益になるためです。また、新人や中堅では対応できない大型案件やトラブル対応を任せることで、組織全体のリスク管理と利益最大化を狙います。
▼KPI例
- 担当部門の粗利目標達成
- 新人同行およびフィードバック実施数
- 社内勉強会の開催(四半期に1回)
▼行動例
- 自身の成功事例を「勝ちパターン」としてマニュアル化し、チームチャットで共有する
- メンバーの商談に同行した際、クロージングではなく「顧客の課題整理」を実演して見せる
- 他部門(開発やCS)と連携し、顧客の声を製品改善に繋げるプロジェクトを主導する
ベテランにはプレーヤーとしての枠を超え、組織の成果を最大化させる「プレイングマネージャー」的視点での目標設定が不可欠です。
設定した営業目標を達成するためのポイント
どれだけ優れた営業目標を立てても、実行と運用が伴わなければ成果にはつながりません。日々の行動への落とし込み、週次レビュー、改善の集中ポイントなど、達成率を高めるための仕組み化が欠かせません。ここからは、達成率を上げる3つのポイントを紹介します。
行動KPIは「日・週単位のタスク」へ細分化する
行動KPIは、日次・週次の具体的なタスクに細分化することで、メンバーが迷わず行動できる状態をつくります。月間KPIだけでは、日々何をすべきかが不明確になり、進捗遅れに気づくのが遅れるリスクがあります。
例えば、「月間新規商談20件」というKPIをそのまま提示しても、「今日何をすべきか」が分からず、後回しになりがちです。
これを日・週単位の行動に落とし込むことで、毎日の業務が明確になり、計画的に目標達成へ進めるようになります。
- 1日2件のアポイントを獲得(週10件)
- 毎朝30分、見込み顧客リストを更新
- 毎週初めに、訪問スケジュールを確定
このようにタスクを具体化すれば、メンバーは「今やるべきこと」を理解し、着実な行動につなげることができます。
週次レビューを仕組み化し、ズレを即時修正する
週次レビューを定例化することで、目標とのズレを早期に発見し、迅速に軌道修正が可能になります。月次や四半期レビューでは、気づいた時点で挽回が難しいケースが多く、リスクが高まります。
週次で進捗を確認すれば、小さなズレの段階で対処でき、大きな未達を未然に防ぐことができます。
確認するポイントは次の3点です。
- 今週の行動KPIの達成状況と未達要因の特定
- 来週の重点アクションと優先順位の整理
- 支援が必要な課題の共有
例えば、商談化率が目標を下回っている場合は、すぐにトークスクリプトを見直したり、ロールプレイを追加したりと、実行可能な改善策に着手できます。
ボトルネックを1つに絞り、リソースを集中させる
営業目標の達成を阻む要因が複数あったとしても、最も影響度の高いボトルネックに絞って改善リソースを集中することが重要です。 課題を一度に解決しようとすると、リソースが分散し、結果的にどれも中途半端に終わる恐れがあります。
限られた時間と人員の中で最大の成果を出すには、ひとつの課題に集中して取り組むのが効果的です。例えば、以下のような状況について考えてみましょう。
- アポ獲得率:目標達成
- 商談化率:大幅に未達(ボトルネック)
- 受注率:目標達成
この場合、商談化率の改善にリソースを集中し、ヒアリング力を高める研修や商談同行の機会を増やすことで、全体のパフォーマンスが大きく向上します。
まとめ
本記事では、営業目標が組織の成果を左右する理由から、具体的な設定手順、有効なフレームワーク、そして階層別の実践例までを解説しました。
営業目標は単なるノルマではなく、経営戦略を現場の行動へと変換する重要な翻訳機です。KGIからの逆算による論理的な設計や、SMART・OKRといったフレームワークを活用し、週次レビューで形骸化を防ぐ。これらを徹底することで、目標は「飾られた数字」から「達成すべき必然の道標」へと変わり、組織全体の生産性は向上します。
しかし、自社の課題に合わせて最適な目標を設計し、運用定着させるには、多角的な視点と専門的なノウハウが必要です。
弊社「CLF PARTNERS株式会社」では、IT、製造、人材など多岐にわたる業界で、累計350社以上の営業支援実績がございます。単なる研修やコンサルティングにとどまらず、「営業コンサルティング×営業研修」の両面からアプローチすることで、半年以上の継続率96.5%という高い成果を実現しています。
営業組織における目標設定から達成までの一貫した支援を行っておりますので、自社の営業目標設定を見直す際、専門家のサポートが必要と感じた場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
この記事の監修者
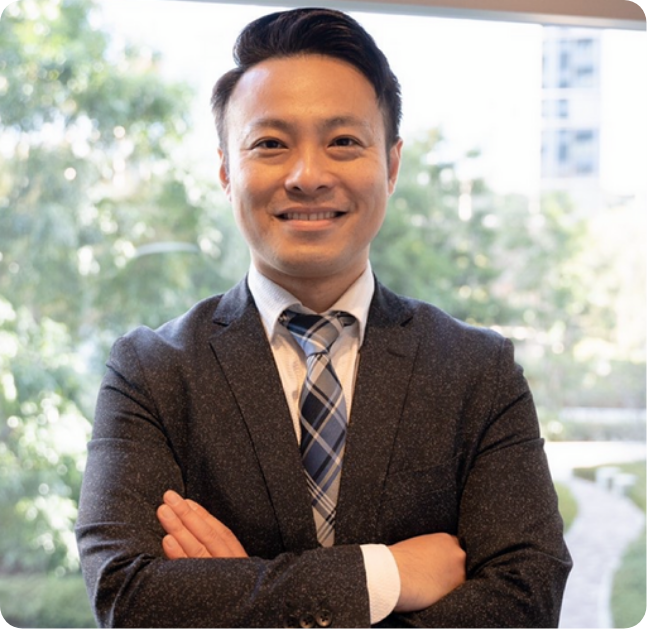
CLF PARTNERS株式会社
代表取締役社長 松下 和誉
大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事
公式Xアカウント:https://x.com/clf_km