営業研修・教育

「営業メンバーのスキルを向上させたいが、日々の実践だけでは体系的な学びが不足している」 「ケーススタディを取り入れた研修を企画したいが、どう設計すればいいかわからない」
「自社の営業プロセスに合ったリアルなケーススタディを作成したいが、ノウハウがない」
こうした課題を抱える営業企画担当者や人事担当者は少なくありません。営業研修は座学やロールプレイだけでは実践力が身につきにくく、かといって現場任せでは属人的なスキルにとどまってしまいます。
そこで注目されているのが、実際の営業シーンを想定した「ケーススタディ」を活用した研修です。
しかし、効果的なケーススタディを設計するには、単なる事例紹介ではなく、自社の営業プロセスに即したリアルなシナリオと、明確な学習目標の設定が不可欠です。
そこで本記事では、営業力を飛躍的に高めるケーススタディの設計方法について、以下のポイントを解説します。
- 営業で成果を上げるためにケーススタディが欠かせない理由
- 営業ケーススタディの主な種類
- 効果的な営業ケーススタディの作り方5ステップ
- BtoB営業で使える具体的な例題と模範解答
CLF PARTNERSでは、営業研修の企画から実施、効果測定まで一貫してサポートしています。
累計350社以上、3,000人以上の営業パーソンを支援してきた実績をもとに、貴社の営業プロセスに完全カスタマイズした「オリジナルケーススタディ」を設計。座学にとどまらず、現場で即実践できる行動変容を促す研修プログラムを提供します。
- 営業メンバーのスキルを体系的に底上げしたい
- 自社の商材や営業プロセスに合ったケーススタディを作りたい
- ディスカッションを通じて、チーム全体の営業力を強化したい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社サービスをご検討ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
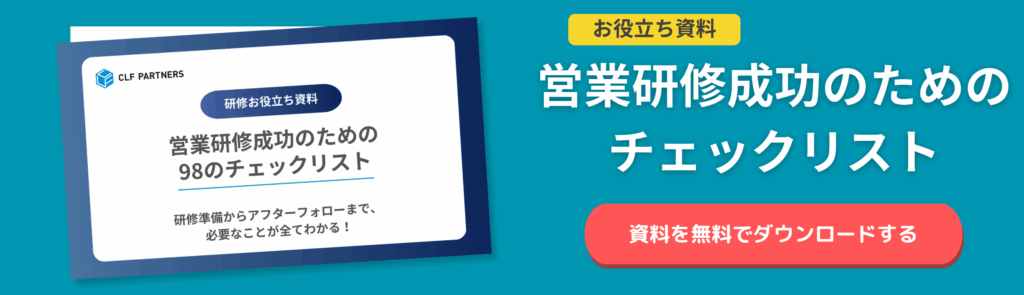
目次
営業におけるケーススタディとは
営業におけるケーススタディとは、実際の営業現場で起こり得る具体的な状況や過去の事例をもとに、最適な解決策を擬似体験しながら学ぶ「実践型の研修手法」です。
単なる知識のインプットを目的とした座学とは異なり、現場で即活用できる「戦略的思考力」と「応用力」の養成を目的としています。
営業組織全体のパフォーマンスを安定的に向上させるには、個々の営業担当者の経験則に頼るのではなく、体系的な学びの仕組みが欠かせません。
ケーススタディでは、例えば以下のようなリアルなシナリオが用いられます。
- 難易度の高い特定顧客へのアプローチ方法の策定
- 重要な失注・成功事例の要因分析
- 競合とのコンペにおける交渉戦略の立案
こうした課題に対して、受講者が主体的に思考し、ディスカッションを通じて最善策を導き出すプロセスを重視します。
ケーススタディは、営業担当者が直面する複雑な課題に多角的に向き合い、柔軟に対応する力を養うための、極めて有効な学習手法です。
営業で成果を上げるためにケーススタディが欠かせない理由
営業スキルは現場経験の積み重ねで磨かれますが、個人差が生まれやすいのが課題です。ケーススタディはその差を埋め、全員の実践力を底上げする最適な手法です。次に、どのような効果が期待できるのか具体的に見ていきましょう。
実践力を養う「疑似体験学習」ができるから
ケーススタディの最大の強みは、失敗のリスクなく実践的な営業場面を経験できる点にあります。現場では一度の失敗が商談機会の喪失につながりますが、ケーススタディでは何度でも試行錯誤が可能です。
実際の営業現場を想定したシナリオに取り組むことで、受講者は以下のような疑似体験を積むことができます。
- 初回商談での顧客ヒアリングの進め方
- 価格交渉時の切り返しトーク
- 競合コンペでの差別化提案
例えば、新人営業が「予算がない」と断られた際の対応を、ケーススタディで事前に学んでおけば、実際の商談で冷静に対処できます。
このように、安全な環境で実践的なスキルを習得できるため、現場配属後の立ち上がりが早くなり、早期戦力化が実現します。結果として、組織全体の営業生産性向上につながるのです。
課題発見力・仮説思考を鍛えられるから
優れた営業パーソンは、顧客の表面的な要望ではなく、その背景にある本質的な課題を見抜く力を持っています。ケーススタディは、この課題発見力と仮説思考を組織的に鍛える有効な手段です。
ケーススタディでは、断片的な情報から顧客の真の課題を推察し、最適な提案を導き出すプロセスを繰り返します。この訓練により、以下のスキルが強化されます。
- 顧客の発言から隠れたニーズを読み取る力
- 仮説を立てて検証する思考プロセス
- 限られた情報から最適解を導く判断力
例えば、「コスト削減したい」という顧客の要望に対し、表面的に価格を下げるのではなく、「業務効率化による人件費削減」という本質的な課題を見抜く訓練ができます。こうした思考プロセスを繰り返すことで、営業メンバー全員が戦略的な提案ができる人材へと成長します。
チーム内の共通認識とナレッジ共有が進むから
営業組織の課題の一つは、トップセールスのノウハウが属人化し、組織全体に浸透しないことです。ケーススタディは、このナレッジを可視化し、チーム全体で共有する最適な仕組みとなります。
ケーススタディを通じたディスカッションでは、メンバー同士が多様な視点やアプローチを交換し合います。この過程で以下のような効果が生まれます。
- トップセールスの思考プロセスの言語化と共有
- 成功・失敗事例から学ぶベストプラクティスの蓄積
- 営業プロセスや用語に関する認識の統一
例えば、ある商談で成功したヒアリング手法をケーススタディ化すれば、それが組織の標準スキルとして定着します。また、ディスカッションを通じて「この場面ではこう対応する」という共通認識が形成され、チーム全体の対応品質が均一化されます。
営業ケーススタディの主な種類
ケーススタディには、解決策を考えるもの、事例を分析するもの、意思決定を迫るものなど、目的に応じたタイプがあります。それぞれに求められる思考の深さが異なります。まずは代表的な4種類を整理しておきましょう。
課題解決型
課題解決型は、顧客の抱える複雑な問題に対し、最適な解決策を論理的に構築する力を養うケーススタディです。現代の営業活動では、単に製品を販売するだけでなく、顧客のビジネス課題に深く入り込み、解決策を提案する力が求められています。
この手法は、顧客の潜在ニーズを発見し、それに応じた解決プロセスを疑似体験するのに最適です。例えば、「売上低迷に悩む中堅製造業A社に対し、自社のMAツールをどのように提案し、KGI(重要目標達成指標)の実現に貢献するか」といったテーマが想定されます。
営業担当者は、A社の現状を分析し、課題を特定したうえで、ツール導入による効果を具体的なシナリオとして示す必要があります。
こうしたプロセスを通じて、顧客のビジネス全体を俯瞰し、課題を明確にした上で解決へ導く「コンサルティング営業」のスキルを、実践的に高めることができます。
事例分析型
事例分析型は、過去の営業活動における成功・失敗の要因を深く掘り下げ、組織全体の営業力を向上させるための手法です。
属人化しがちな営業ノウハウを「形式知」として共有することで、成功の再現性を高め、失敗の未然防止につなげます。
例えば、「大型案件の失注」というケースを取り上げ、次の観点から多角的に分析を行います。
- 初期アプローチのタイミングと方法
- キーマンの特定および関係構築の過程
- 競合との差別化ポイントの提示
- 提案内容と顧客ニーズの整合性
- クロージング過程での課題
これにより、「決裁者へのアプローチが遅れた」「競合の強みを正しく把握できていなかった」など、具体的な敗因を明らかにし、次に活かす改善策を導き出します。
経験を組織的な学びへと昇華し、営業プロセスの標準化・高度化を目指すうえで、極めて有効なアプローチです。
意思決定型
意思決定型は、営業現場における重要な選択の場面で、限られた情報の中から最善の判断を下す力を養うケーススタディです。現実の営業活動では、時間・人員・コストなどのリソース制約や、不確実な情報の中で意思決定を迫られることが頻繁にあります。
例えば、「A社とB社という有望な2社に対し、対応可能なリソースが1名分しかない」といった状況で、次の要素を比較検討し、優先すべき案件を選定します。
- 受注確度と期待収益
- 案件の規模(LTV:顧客生涯価値)
- 導入決定までのリードタイム
- 自社戦略における優先順位
この際、単に選択肢を決めるだけでなく、「なぜその判断に至ったのか」という論理的根拠と意思決定基準を明確にすることが求められます。
営業戦略の立案やリソース配分を担うマネージャー層にとって、大局的な視野を持った判断力を磨くための実践的トレーニングです。
ロールプレイング連携型
ロールプレイング連携型は、他のケーススタディで培った分析・設計内容を、商談や顧客対応といった実践の場で再現するトレーニングです。「知っている」から「できる」へと、知識を実行力に変えるプロセスとして位置づけられます。
例えば、「(課題解決型で検討した)MAツールの提案」をテーマに設定し、参加者が営業役と顧客役に分かれて以下のような場面を演じます。
- 初回訪問でのヒアリング
- 難色を示す役員へのプレゼンテーション
重要なのは、演技そのものではなく、設定された顧客課題や状況に即して、適切なコミュニケーションを取れているかを検証することです。
ロールプレイング連携型は、分析力・戦略的思考を、現場で活用できる実行力へと転換するための、教育の仕上げとして欠かせないプロセスです。
効果的な営業ケーススタディの作り方|5ステップ
営業力を高めるケーススタディを設計するには、目的設定からシナリオ構築、問いの設計まで体系的な手順が必要です。以下の5ステップを押さえれば、学びが「行動変容」に直結する設計が可能になります。それぞれ順に解説します。
ステップ1:研修の目的とゴール(到達目標)を明確にする
効果的なケーススタディは、明確な目的設定から始まります。何を学ばせたいのかが曖昧なまま設計すると、議論が散漫になり、現場での行動変容につながりません。
目的を設定する際は、組織の課題と紐づけて、測定可能な到達目標を定めることが重要です。具体的には以下のような観点で整理します。
- 解決すべき営業組織の課題(受注率の低下、商談期間の長期化など)
- 強化したいスキル(ヒアリング力、提案力、交渉力など)
- 研修後に期待する行動変容(初回訪問での情報収集項目の増加など)
例えば、「新規商談の受注率を20%から30%に引き上げる」という組織目標がある場合、「顧客の潜在ニーズを引き出すヒアリング力を強化し、初回訪問での課題発見率を向上させる」といった具体的なゴールを設定します。
このように目的が明確であれば、それに沿ったシナリオ設計が可能になり、研修効果の測定もしやすくなります。結果として、投資対効果の高い研修が実現します。
ステップ2:自社の営業プロセスに即したリアルなシナリオを作成する
ケーススタディの学びを現場で活かすには、自社の営業プロセスに即したリアルなシナリオが不可欠です。一般論や他社事例では、受講者が自分事として捉えにくく、実践につながりません。
シナリオ作成では、自社が実際に直面する状況を忠実に再現することが重要です。具体的には以下の要素を盛り込みます。
- 自社の商材・サービスの特性と競合優位性
- ターゲット顧客の業界特性や組織構造
- 実際の営業プロセス(アプローチ、商談、提案、クロージング)
たとえば、人事向けSaaSを販売している企業であれば、「従業員300名の製造業で、Excel管理に限界を感じている人事部長へのアプローチ」といった具体的なシナリオを設定します。
その際、「経営層は費用対効果を重視」「現場は操作の簡便性を求める」といった複数の意思決定者の視点も盛り込むことで、よりリアリティが増します。
ステップ3:顧客情報、競合情報、自社の状況など詳細な背景を設定する
リアルなケーススタディには、商談を取り巻く詳細な背景情報が欠かせません。情報が不足していると、受講者は表面的な議論にとどまり、深い思考が促されません。
背景設定では、実際の営業活動で入手できる情報レベルに合わせて、以下の項目を具体的に記載します。
- 顧客企業の基本情報(業種、規模、事業内容、経営課題)
- 担当者のプロフィール(役職、決裁権限、関心事項)
- 競合他社の動向(提案内容、価格帯、強み・弱み)
- 自社の状況(納期、在庫、値引き余地、過去取引実績)
例えば、「顧客企業は創業50年の老舗製造業、売上100億円、従業員500名。人事部長は40代後半で、経営層からDX推進を命じられているが、現場の抵抗を懸念している。競合A社は低価格を武器に提案中、B社は導入実績の豊富さを訴求」といった詳細な情報を提示します。
これにより、受講者は多角的な視点で戦略を考える訓練ができます。結果として、実際の商談でも状況判断力が向上します。
ステップ4:受講者に考えてほしい「問い」や「課題」を具体的に盛り込む
ケーススタディの学習効果は、どのような「問い」を設定するかで大きく変わります。抽象的な問いでは思考が浅くなり、具体的すぎると考える余地がなくなります。
効果的な問いは、受講者に多面的な思考を促し、現場で応用可能な判断基準を養うものです。具体的には以下のような設計が有効です。
- 状況分析を促す問い(この顧客の本質的な課題は何か)
- 戦略立案を促す問い(どのようなアプローチが最適か)
- 意思決定を促す問い(複数の選択肢からどれを選ぶべきか)
- 実行計画を促す問い(次回訪問までに何を準備すべきか)
例えば、「人事部長は『予算がない』と言っているが、本当の懸念は何だと考えられるか」「競合が低価格を提示している中で、どう差別化すべきか」「初回訪問で何を聞き出し、どのような提案につなげるか」といった具体的な問いを設定します。
ステップ5:議論のポイントや「模範解答」の骨子を準備する
ケーススタディの効果を最大化するには、ファシリテーター向けの議論ガイドと模範解答が必要です。これがないと、議論が脱線したり、誤った学びで終わったりするリスクがあります。
議論ガイドでは、受講者に気づいてほしいポイントと、そこに導くための質問を整理します。具体的には以下の内容を準備します。
- 議論で触れるべき重要な観点(顧客心理、競合対策、リスク管理など)
- 受講者の思考を深めるための追加質問
- 陥りやすい誤解や見落としがちなポイント
- 複数の正解パターンとその評価基準
例えば、「価格交渉の場面」では、「安易な値引きは避け、まず顧客の予算制約の背景を確認する」「ROIを具体的に示し、投資対効果で納得させる」「導入後のサポート体制など、価格以外の価値を訴求する」といった複数のアプローチを模範解答として用意します。
また、「この場面で即座に値引きすると、どのようなリスクがあるか」という問いかけで、受講者自身に気づかせる設計も重要です。
なお、最近ではAIを活用することで、ケーススタディの作成効率を大幅に向上させることも可能です。過去の商談データや成功事例をAIで分析し、リアルなシナリオを自動生成したり、受講者の回答をAIが即座に評価してフィードバックを返したりする仕組みも登場しています。
ケーススタディ設計の大前提:自社の提供価値とペルソナの共通認識
ここまで5つのステップを解説しましたが、実はこれらを実践する前に、営業チーム全体で押さえておくべき重要な前提条件があります。それが「自社の提供価値とターゲットペルソナの共通認識」です。
どれだけ精巧なケーススタディを設計しても、この土台がなければ、議論は表面的になり、現場で使えるスキルは身につきません。
チーム全体で共有すべき3つの要素は以下の通りです。
1. 自社サービスの特徴と独自の提供価値
顧客のどのような課題を解決できるのか、競合他社と比較した際の差別化ポイントは何か、顧客が得られる具体的な成果(定量・定性)は何かを明確にします。単なる機能の羅列ではなく、「顧客視点での価値」として言語化することが重要です。
2. ターゲットペルソナの明確化
業種、企業規模、役職などの属性だけでなく、抱えている課題や痛み、意思決定プロセスと判断基準、情報収集の方法や重視するポイントまで具体的に定義します。複数のペルソナが存在する場合は、それぞれの特性を整理しておきます。
3. 顧客ニーズと自社価値のマッチング
どのペルソナに、どの価値を、どう訴求するかを明確にします。ペルソナごとの最適なアプローチ方法や、商談の各フェーズで伝えるべきメッセージを整理しておくことで、ケーススタディの設計がスムーズになります。
このように、「誰に・何を・どう売るか」の共通認識がすべての土台です。この前提がしっかりしていれば、5つのステップで作成したケーススタディは、営業チーム全体の実践力を飛躍的に向上させる強力なツールとなります。
BtoB営業ケーススタディの「例題」と「模範解答」
ここからは、実際にBtoB営業で使える具体的なケースを紹介します。リアルな営業シーンを想定しながら、受講者が考え、議論し、行動に落とし込むプロセスをイメージしてみましょう
例題①:新規開拓(テレアポでの切り返し)
あなたは人事向け勤怠管理SaaS「WorkFlow」の営業担当です。従業員300名の製造業A社の人事部に架電したところ、人事課長から以下の反応がありました。
「勤怠管理システムですか。実は半年前に他社のシステムを導入したばかりなんです。今のところ大きな不満もないですし、新しいシステムを検討する予定はありません」
現在使用しているのは競合B社の製品で、月額30万円。A社は最近、働き方改革への対応や残業時間の可視化が経営課題として挙がっており、人事部門には業務効率化のプレッシャーがかかっています。
問い
この状況で、あなたはどのように切り返し、次のステップ(アポイント獲得または情報提供の機会)につなげますか。具体的な切り返しトークを考えてください。
実践的な進め方
| フェーズ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 個人ワーク | 10分 | 切り返しトークを各自で考案し、シートに記入 |
| ペアワーク | 10分 | 2人1組でロールプレイ(営業役・顧客役を交代) |
| グループディスカッション | 15分 | 4〜6名のグループで効果的だったアプローチを共有 |
| 全体共有 | 10分 | 各グループの代表が発表、講師が重要ポイントを解説 |
| 講師フィードバック | 10分 | 模範解答の提示と実践での注意点の説明 |
模範解答のポイント
効果的な切り返しは、単なる否定への対応ではなく、「潜在的な課題」に気づいてもらうきっかけを作ることです。以下の3つの要素を組み合わせます。
- 現状システムの肯定から入り、警戒心を解く
- 顧客が気づいていない課題や変化を提示する
- 情報提供という形で、次の接点を作る
模範解答例
「導入されたばかりなんですね。それでは基本的な勤怠管理はカバーできていると思います。実は最近、製造業のお客様から『勤怠データは取れているが、それを経営判断に活かせていない』というお声をよくいただくんです。
例えば、部署ごとの残業時間の推移から、業務の偏りや人員配置の最適化を可視化するといった活用ですね。もし御社でも働き方改革や業務効率化がテーマになっているようでしたら、他社の活用事例をまとめた資料だけでもお送りできますが、いかがでしょうか」
総括
このアプローチでは、現状システムを否定せず、「さらに上のレベルの活用」という視点を提示しています。また、「資料送付」という低いハードルで次の接点を作ることで、関係構築の第一歩につなげます。
例題②:商談(初回訪問でのヒアリング)
人事評価システム「評価ナビ」の初回商談です。従業員500名のIT企業C社を訪問し、人事部長と面談することになりました。事前情報では「現在Excelで評価を管理しているが、集計に時間がかかり、フィードバックが遅れがち」という課題があると聞いています。
商談冒頭、人事部長から「評価業務の効率化を検討していて、いくつかシステムを見ているところです。御社のシステムでできることを教えてください」と言われました。
問い
初回訪問で顧客の本質的な課題を引き出すために、どのような順序でヒアリングを進めますか。具体的な質問例を3〜5つ挙げてください。
実践的な進め方
| フェーズ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 個人ワーク | 10分 | ヒアリング項目と質問を各自で設計 |
| グループディスカッション | 20分 | 4〜6名で質問の順序と意図を議論、ベストな流れを作成 |
| ロールプレイ | 15分 | グループ内で営業役・顧客役に分かれて実践 |
| 全体共有 | 10分 | 効果的だった質問例を全体で共有 |
| 講師フィードバック | 10分 | 「事実→背景→影響→理想」の質問構造を解説 |
模範解答のポイント
効果的なヒアリングは、表面的な課題から本質的なニーズへと段階的に深掘りする構造が重要です。「事実→背景→影響→理想」の4段階で質問を設計します。
- 事実確認: 現状の業務フローやプロセスを把握する
- 背景理解: その状況になった経緯や理由を探る
- 影響分析: 課題が組織や業務に与える影響を明確にする
- 理想の姿: 顧客が本当に実現したい状態を引き出す
模範解答例
| 質問分類 | 質問内容 |
|---|---|
| 事実確認の質問 | 現在の評価プロセスは、具体的にどのような流れで進めていらっしゃいますか。評価シートの配布から集計、フィードバックまで、どれくらいの期間がかかっていますか。 |
| 背景理解の質問 | Excelでの運用を続けてこられた理由は何でしょうか。また、今のタイミングでシステム化を検討されている背景を教えていただけますか。 |
| 影響分析の質問 | 評価業務に時間がかかることで、人事部門や現場のマネージャーにはどのような影響が出ていますか。フィードバックの遅れによって、メンバーのモチベーションや育成面で課題を感じることはありますか。 |
| 理想の姿を引き出す質問 | もし評価業務が効率化されたとして、その時間を人事部門として何に使いたいとお考えですか。理想的には、評価制度をどのような状態にしたいとお考えでしょうか。 |
総括
このように段階的に質問することで、「Excelの集計が大変」という表面的な課題から、「評価を通じた人材育成を強化したいが、業務に追われて実現できていない」という本質的なニーズまで引き出すことができます。
この情報があれば、単なる効率化ツールではなく、「人材育成を支援するシステム」として提案の角度を変えることが可能になります。
例題③:提案・交渉(競合他社とのコンペ)
採用管理システム「採用プラス」のコンペ最終プレゼンです。従業員200名のIT企業D社は、事業拡大に伴い年間50名の中途採用を予定しており、応募者管理と選考プロセスの効率化が急務となっています。
コンペには3社が参加しており、状況は以下の通りです。
- 競合E社:業界最大手、月額25万円(自社は月額35万円)
- 競合F社:新興企業、月額20万円で多機能を訴求
- 自社:中堅だが、IT・ベンチャー企業での導入実績が豊富
先日の提案で、D社の人事部長から「機能的にはどこも大差ないように見える。正直、コストを抑えられるE社かF社に傾いている」というフィードバックがありました。
問い
価格で劣る状況の中で、最終プレゼンでどのように差別化し、自社を選んでもらいますか。提案の切り口と具体的な訴求ポイントを考えてください。
実践的な進め方
| フェーズ | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 個人ワーク | 15分 | 差別化ポイントと提案シナリオを各自で設計 |
| グループディスカッション | 20分 | 4〜6名で提案戦略を議論、最も効果的なアプローチを選定 |
| プレゼン準備 | 30分 | グループで3分間の提案プレゼンを作成 |
| グループ発表 | 15分 | 各グループが提案を発表(3分×5グループ) |
| 講師フィードバック | 10分 | 価格競争に巻き込まれない差別化戦略を解説 |
模範解答のポイント
価格競争に巻き込まれず、自社を選んでもらうには、「価格」ではなく「価値」で勝負する戦略が必要です。具体的には以下の3つの要素で差別化します。
- 成果保証: 導入後の成果を具体的に約束する
- 導入支援: システム導入だけでなく、業務改善まで伴走する
- 再現性: 同業他社での成功事例を具体的に示す
模範解答例
「お見積りの件、承知いたしました。確かに機能面では各社とも大きな差はないかもしれません。ただ、私たちがD社様にご提案したいのは『システム』ではなく『採用業務の成果向上』です」
「実は当社では、人材業界のお客様に特化した導入支援プログラムを用意しています。具体的には、システム導入後3カ月間、専任のカスタマーサクセス担当が週次でミーティングを行い、以下をサポートします」
- 応募者対応スピードを平均30%短縮する業務フロー設計
- 選考通過率を可視化し、採用基準の最適化を支援
- 採用担当者向けのシステム活用勉強会(月2回)
「すでに同規模の人材会社G社様では、導入後6カ月で『応募から内定までの期間を20日から14日に短縮』『採用担当者の残業時間を月30時間削減』という成果が出ています。こちらの詳細なレポートをお持ちしました」
「初期費用は確かに他社より高くなりますが、この導入支援により、確実に成果を出していただける自信があります。仮に6カ月で採用期間を6日短縮できれば、採用担当者の工数削減だけで月額費用の差は十分に回収できる計算です」
総括
このアプローチでは、価格の高さを「投資対効果」の観点で正当化し、さらに同業他社での具体的な成果データで信頼性を担保しています。また、「システム販売」ではなく「成果へのコミット」という価値提案にシフトすることで、価格以外の判断軸を提示することができます。
営業現場を変える、CLF PARTNERSのリアルケーススタディ設計
CLF PARTNERSでは、累計350社以上、3,000人以上の営業パーソンを支援してきた実績をもとに、貴社の営業プロセスに完全カスタマイズしたオリジナルケーススタディを設計します。
貴社の実際の製品・サービスとクライアント事例をもとに作成するため、明日からでも現場で使えるリアルなケーススタディが完成します。
単なる教科書的な内容ではなく、貴社が直面する商談シーンや顧客の反応を忠実に再現し、新規開拓、商談、提案、交渉など、各フェーズで求められる判断力と実践力を徹底的に鍛えます。
さらに、ケーススタディの実施だけで終わらせず、現場での行動変容まで伴走する点が当社の強みです。研修後のフォローアップや個別フィードバックを通じて、学びを確実に成果へとつなげます。
営業コンサル と 営業研修 の両面から貴社の課題を解決し、自走できる営業組織への変革を実現します。
営業力の底上げとチーム全体の成果向上を本気で目指すなら、ぜひ一度ご相談ください。
▶ 【月3社限定】営業組織の課題診断+改善策提案(60分無料)はこちら
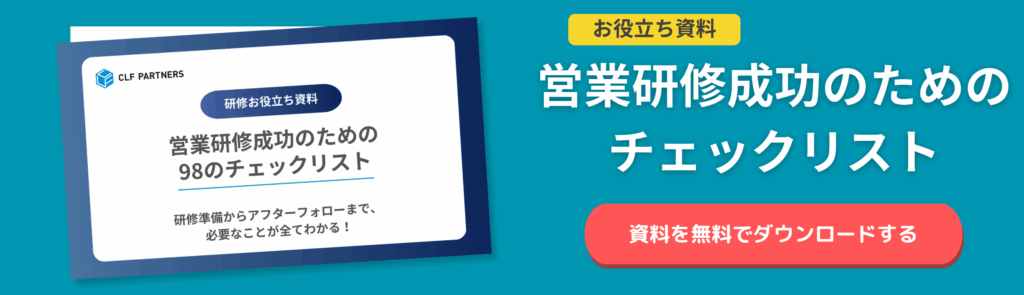
まとめ
営業ケーススタディは、実際の営業現場で起こり得る具体的な状況を題材に、最適な解決策を疑似体験しながら学ぶ実践型の研修手法です。失敗のリスクなく実践的なスキルを習得でき、顧客の本質的な課題を見抜く力や、トップセールスのノウハウを組織全体で共有する仕組みとして機能します。
効果的なケーススタディを設計するには、研修の目的とゴールを明確にし、自社の営業プロセスに即したリアルなシナリオを作成することが重要です。さらに、顧客情報や競合情報などの詳細な背景設定と、受講者の思考を深める具体的な問いの設計、そして議論を導く模範解答の準備が欠かせません。
営業組織の課題は、個人のスキルに依存する属人的な営業体制から、組織全体で成果を上げられる仕組みへの転換です。ケーススタディは、その実現に向けた最も効果的な手法の一つです。
CLF PARTNERSでは、貴社の営業プロセスに完全カスタマイズしたオリジナルケーススタディを設計し、現場での行動変容まで徹底的に伴走します。営業メンバーのスキルを体系的に底上げし、自走できる強い営業組織への変革を目指すなら、ぜひ一度ご相談ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
この記事の監修者
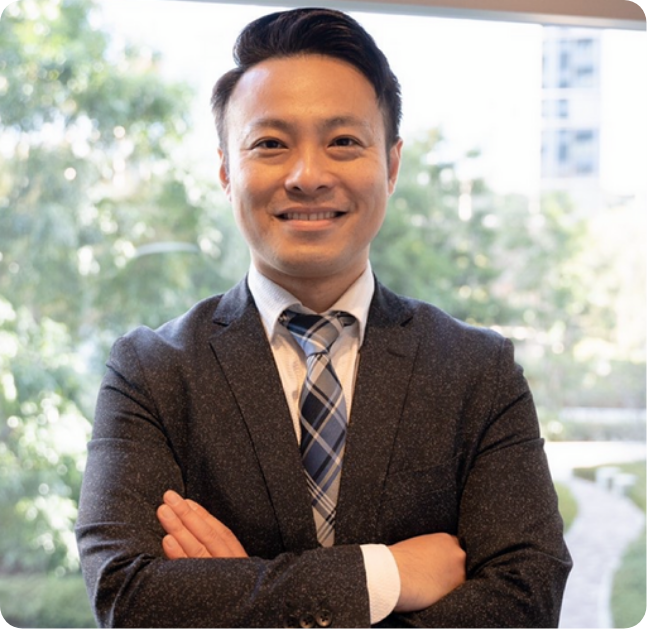
CLF PARTNERS株式会社
代表取締役社長 松下 和誉
大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事
公式Xアカウント:https://x.com/clf_km






