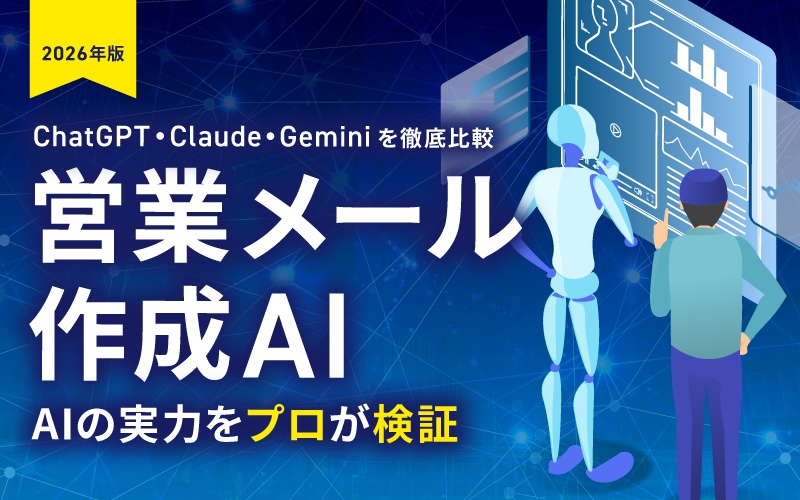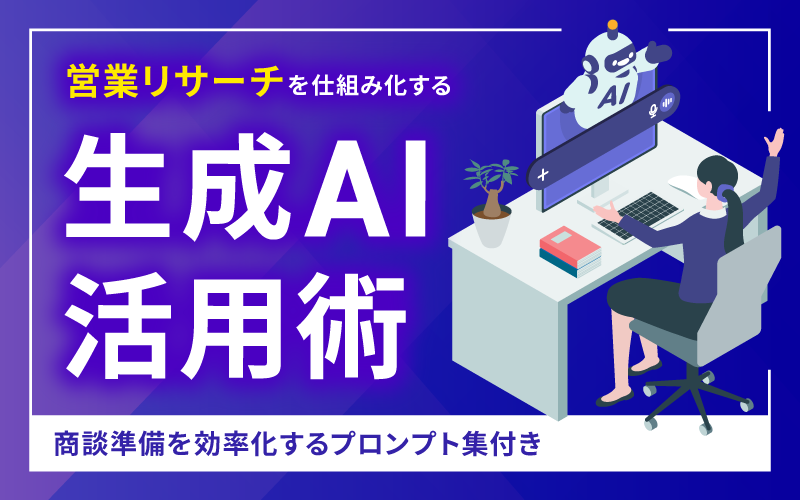営業研修・教育

「研修を実施したいが、上司や経営層にどう説明すればいいかわからない」
「研修予算の稟議を通すために、費用対効果を示す必要があるが、算出方法がわからない」
「研修を実施しても、その効果を定量的に証明できず、次年度の予算確保が難しい」
こうした課題を抱える人事担当者や営業企画担当者は少なくありません。研修は「実施すること」自体が目的化しやすく、投資効果が見えにくいため、経営層への説得材料を用意するのが困難です。
そこで本記事では、研修の費用対効果(ROI)を算出し、経営層を納得させるために押さえておきたい以下のポイントを解説します。
- 研修ROIの算出が経営層への説得に必要な理由
- 決裁者を納得させる研修ROIの考え方
- 研修ROIを具体的に計算する5つのステップ
- 稟議書の作成例と実践的な活用方法
CLF PARTNERSでは、営業研修の企画から実施、効果測定、ROI算出まで一貫してサポートしています。
累計350社以上、3,000人以上の営業パーソンを支援してきた実績と、再現性の高い独自メソッドにより、貴社の研修投資を「成果の見える投資」へと変革します。
- 研修の費用対効果を明確にして、経営層を説得したい
- 稟議を通すための具体的な数値根拠が欲しい
- 研修効果を測定し、次年度の予算確保につなげたい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社サービスをご検討ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
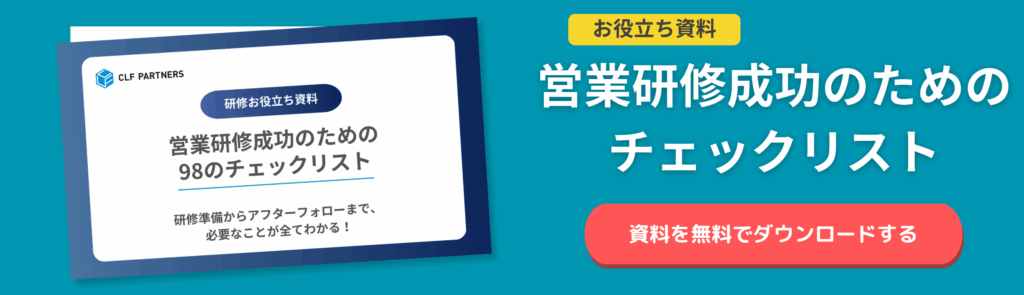
目次
研修ROIの算出が稟議や経営層への説得に必要な理由
研修を導入したい担当者にとって、経営層への説明で最も重要なのが「費用対効果の明確化」です。数値的根拠がなければ、どれほど有益な施策でも投資判断は得られません。ここでは、ROI算出が説得力を高める3つの理由を解説します。
理由1:経営層への説明責任(アカウンタビリティ)のため
人的資本経営の流れの中で、研修は「費用」ではなく「投資」として説明責任が求められるようになりました。そのため、ROIを明示することで、「どの程度の成果を見込める投資なのか」を定量的に伝えられます。
特に営業研修では、売上や受注率などの成果指標と紐づけやすく、経営層への説得材料として機能します。
理由2:投資判断・優先順位づけのため
限られた人材開発予算の中で、どの施策に投資するかを決める材料としてROIが機能します。営業研修やマネジメント研修など、成果の見えやすいプログラムはROI算出により意思決定を後押しできるため、稟議の通過率を高めることができます。
複数の施策候補がある場合、ROIの比較により優先順位を明確にできます。
理由3:研修効果を可視化し、次年度の投資につなげるため
一度の研修で終わらせず、成果を定量的に示すことで次年度予算の確保や継続的な改善サイクルが可能になります。
実際、従業員1人あたりの教育研修費用は34,606円となっており、コロナ禍を経て企業の研修費用は増加傾向にあります。また、今後1〜3年で約6割の企業が教育研修費用総額を「増加させる見込み」と回答しており、ROIを示せる企業が予算を獲得しやすい状況です。
決裁者を納得させる研修ROIの考え方
ROIを提示するだけでは十分ではありません。経営層が納得するためには、研修を「費用」ではなく「投資」として捉え、再現性ある評価軸で語ることが不可欠です。ここでは、ROIを正しく伝えるための3つの視点を紹介します。
「コスト(費用)」ではなく「インベストメント(投資)」として捉える
研修費用を「コスト」ではなく「投資」として捉えることが、経営層への説得において最も重要です。人的資本投資は明確なリターンを生み出すことが実証されているからです。
内閣府の調査によると、従業員一人当たりの人的資本投資額を1%増加させることで、労働生産性が約0.6%向上する可能性が示されています。つまり、研修に投じた費用は、生産性向上という形で企業に還元される「投資」なのです。
特に営業研修では、売上や受注率などの成果指標と直接紐づけやすく、投資対効果を可視化しやすい特徴があります。
したがって、稟議書では「年間○○万円のコスト増」ではなく、「生産性○%向上により、○○万円の付加価値創出を見込む投資」という表現を用いることで、決裁者の投資判断を促すことができます。
納得度を高める「カークパトリックの4段階評価」
研修ROIを算出する際、最も説得力のある手法が「カークパトリックの4段階評価」です。なぜなら、研修効果を体系的に測定し、投資判断に必要な定量データを提供できるからです。
この評価法は、研修効果を以下の4段階で測定します。
| レベル | 評価項目 | 測定方法 | 測定時期 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 反応(満足度) | アンケート | 研修直後 |
| レベル2 | 学習(理解度) | テスト・レポート | 数日後 |
| レベル3 | 行動(実践度) | 行動チェックリスト | 数か月後 |
| レベル4 | 結果(業績影響) | ROI指標(売上・受注率など) | 6か月〜1年後 |
特に営業研修では、レベル3の行動変容(商談プロセスの改善等)とレベル4の結果(売上向上)を明確に示すことで、経営層への説得力が格段に高まります。
したがって、稟議書ではこの4段階評価を用いて、段階的な効果測定計画を提示することが重要です。
研修効果を金額換算する「フィリップスROIモデル」
より経営層の納得を得るには、カークパトリックモデルにROI(投資対効果)を加えた「フィリップスROIモデル」が有効です。研修効果を具体的な金額で示すことで、投資判断の明確な根拠となるからです。
フィリップスモデルでは、カークパトリックの4段階に「レベル5: ROI」を追加し、以下の計算式で費用対効果を算出します。
| レベル | 評価項目 | 測定内容 | 測定時期 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 反応(満足度) | アンケート | 研修直後 |
| レベル2 | 学習(理解度) | テスト・レポート | 数日後 |
| レベル3 | 行動(実践度) | 行動チェックリスト | 数か月後 |
| レベル4 | 結果(業績影響) | 売上・受注率などの業績指標 | 6か月〜1年後 |
| レベル5 | ROI(投資対効果) | 金額換算した費用対効果 | 6か月〜1年後 |
ROI計算式
ROI(%)=(研修による利益 – 研修コスト)÷ 研修コスト × 100
活用例(営業研修の場合)
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 研修コスト | 200万円 |
| 利益増加額(研修効果) | 500万円 |
| 計算式 | (500万円 − 200万円) ÷ 200万円 × 100 |
| ROI | 150% |
ただし、レベル4(業績)やレベル5(ROI)は、市場環境や他部署の貢献など研修以外の要因も影響するため、測定が困難です。
したがって、稟議書では「レベル3の行動変容を主軸」としつつ、「レベル5のROI試算を参考値」として提示することで、説得力と現実性のバランスを保つことができます。
レベル3の行動変容の具体例(営業研修の場合)
レベル3では、研修で学んだ内容が実際の営業現場で実践されているかどうかを測定します。例えば、ソリューション営業研修の場合、以下のような行動指標を設定します。
- 商談前に顧客情報を調査する事前準備を100%実施している
- 80%以上の商談で、ヒアリングシートを用いて顧客課題の把握を行っている
- 提案書に顧客の課題とその解決策を明記している割合が90%以上に達している
- 商談後の振り返りとフィードバックを週次で継続的に実施している
これらの行動が実際に定着しているかは、上長による行動観察、行動チェックリストの活用、商談同行などを通じて、3か月後および6か月後に測定します。
レベル3において行動変容が確認されれば、レベル4(業績向上)への移行可能性が高まるため、経営層への説明においても十分な説得材料となります。
【実践】研修ROIを具体的に計算する5ステップ
研修ROIの重要性や考え方を理解したところで、具体的な算出方法を見ていきましょう。ROIの計算は、目的の明確化からコストの洗い出し、成果の測定、そして稟議への活用まで、決まった手順を踏むことで誰でも実施できます。
STEP1:研修の目的と成果指標(KPI)を明確にする
ROI算出を成功させるには、「何を改善するための研修なのか」を具体的に定義することが大切です。曖昧な目標設定では、研修後の効果測定ができず、ROI算出も不可能になります。
営業研修であれば、以下のような数値と期限を明確にした目標を設定します。
- 新規顧客からの受注件数を月平均3件から5件に増やす
- 提案から受注までの期間を90日から60日に短縮する
- 平均顧客単価を100万円から150万円に引き上げる
この際、行動指標と結果指標の両方を設定すると効果的です。
例えば行動指標として「週次の新規商談数10件以上」、結果指標として「四半期売上20%向上」といった具合です。目標が明確であればあるほど、研修設計も効果測定もブレることなく進められます。
STEP2:投入コストをすべて洗い出す
研修の真のコストを把握するには、目に見える費用だけでなく、隠れたコストまで含めて計算する必要があります。多くの企業が計上漏れしやすいのが「機会費用」です。
具体的には、以下のコストを漏れなく計上します。
直接費用
- 外部講師料
- 教材費
- 会場費
- eラーニングシステム利用料
間接費用(機会費用)
- 受講者が研修に参加している時間の人件費(時給×研修時間×人数)
- 人事担当者の企画・運営工数
- 事前課題や事後フォローにかかる時間
例えば、年収600万円の社員(時給約3,000円)20名が8時間の研修を受講する場合、人件費だけで48万円が発生します。
内閣府の調査では人的資本投資の64%が機会費用という結果もあり、この部分を見落とすと実態と大きく乖離したROIになってしまいます。
STEP3:研修成果を数値で測定する
設定したKPIに基づき、研修前後のデータを収集して成果を数値化します。測定の精度を高めるポイントは、「研修受講者」と「非受講者」を比較することです。
例えば、営業部30名のうち20名が研修を受講した場合、残り10名の業績推移と比較することで、外部環境の影響を除外した純粋な研修効果を抽出できます。
測定のポイント
- 研修前3か月間の平均値をベースラインとする
- 研修後3か月・6か月・12か月の推移を追跡する
- 結果指標(売上、受注率など)と行動指標(商談プロセス実践率、提案書作成数など)を同時に測定する
データは可能な限り定量的に記録することで、因果関係が明確になります。
STEP4:ROIを算出する
収集したデータをもとに、フィリップスのROI計算式「ROI(%)=(研修による利益 – 研修コスト)÷ 研修コスト × 100」を用いて投資対効果を算出します。
計算の際に重要なのは、「売上増加」ではなく「利益増加」を用いることです。例えば研修後に売上が1,000万円増加しても、利益率が20%であれば利益増加は200万円です。
ROI判断の目安
- ROI 150〜300%:適正値の範囲内で投資効果が高い
- ROI 100〜150%:投資は成功、改善余地あり
- ROI 100%未満:改善が必要
一般的に、研修投資のROI適正値は150%〜300%(1.5倍〜3倍)とされており、この範囲内であれば効果的な投資と判断できます。
ただし、研修効果は長期的に現れることも多いため、初年度のROIが低くても、2年目・3年目の予測値も含めて総合的に評価することが重要です。
STEP5:結果を稟議・経営報告に活かす
算出したROIは、次年度予算の獲得や経営層への報告で活用します。効果的な報告のポイントは、「定量データ」と「定性データ」を組み合わせることです。
報告に含めるべき内容
- ROI数値と計算根拠
- 受講者の行動がどう変わったか
- 顧客からの評価がどう向上したか
- 改善点と次回への施策
また、改善点も正直に報告することで信頼性が高まります。例えば「レベル3の行動変容は目標の80%を達成したが、レベル4の業績向上は市場環境の影響もあり60%にとどまった。次回は事前の現場ヒアリングを強化し、より実践的な内容にブラッシュアップする」といった具合です。
「稟議を通すための具体的な数値根拠が欲しい」とお悩みの方は、まずは無料の課題診断をご活用ください。
貴社の営業組織の現状を分析し、ROI設計を含めた具体的な改善策をご提案します。
▶ 【無料】営業組織の課題と対策を壁打ちしてもらう
営業研修の稟議書テンプレートを無料ダウンロード
本記事で解説した内容をもとに作成した「営業研修実施に関する稟議書テンプレート」を無料でダウンロードいただけます。
このテンプレートには以下の内容が含まれています。
- カークパトリックの4段階評価に基づくKPI設定
- フィリップスROIモデルによる投資対効果の試算(6か月・12か月・24か月)
- 研修コストの詳細(直接費用・間接費用)
- リスクと対策
個人情報の入力なしで、すぐにダウンロードできます。貴社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。
▶ 稟議書テンプレートをダウンロードする
研修ROIを組織改善と次年度計画に反映させるポイント
研修ROIの算出は、ゴールではなくPDCAサイクルのスタートです。算出した結果を分析し、組織改善や次年度の計画に活かしてこそ、研修投資は最大化されます。
ここでは、ROIの結果を「やりっぱなし」にせず、未来の成果につなげるための3つの実践的なポイントを解説します。
ROI結果をチーム・経営の両方向にフィードバックする
研修ROIの分析結果は、現場チームと経営層の両方に適切にフィードバックすることで、組織全体の改善につながります。なぜなら、それぞれの立場で求める情報や活用目的が異なるからです。
現場チームには、レベル3(行動変容)を中心に具体的な改善ポイントをフィードバックします。例えば以下のような内容です。
- どの行動が成果につながったか
- 実践できている人と実践できていない人の差は何か
- 次に取り組むべき具体的なアクション
一方、経営層には、レベル4・5(業績とROI)を中心に投資対効果を報告します。具体的には「ROI 150%を達成し、次年度は対象者を拡大することで年間3,000万円の利益貢献を見込む」といった経営判断に必要な情報を提供します。
このように、受け手に応じた情報提供により、組織全体で研修の価値を共有し、継続的な改善サイクルを回すことができます。
成果要因を分析し、再現可能な仕組みに落とし込む
ROIが高かった研修の成功要因を分析し、再現可能な仕組みとして標準化することで、組織全体の営業力を底上げできます。したがって、「なぜ成果が出たのか」を徹底的に分解することが重要です。
成功要因の分析では、以下の視点で掘り下げます。
- 研修内容のどの部分が最も効果的だったか
- 行動変容を促した現場の支援体制は何か
- 成果を出した受講者に共通する特徴は何か
- 研修前後のフォローアップで効果的だった施策は何か
例えば、「上長による週次の1on1と実践機会の提供が行動定着を促進した」という要因が判明した場合、次回研修では上長向けの事前説明会を必須化し、1on1のガイドラインを整備します。
また、成果を出した営業担当者の商談プロセスを分析し、ベストプラクティスとして全社に展開することで、研修効果を組織全体に波及させることができます。
ROIを次年度の人材開発計画・稟議に反映する
算出したROIは、次年度の人材開発計画や研修予算の稟議において、最も説得力のある根拠となります。過去の実績データに基づいた投資提案は、経営層の意思決定を大きく後押しするからです。
次年度計画への反映では、以下の要素を盛り込みます。
- 今年度のROI実績と達成要因
- 次年度の研修対象者と期待効果
- 投資額と予測ROIの具体的な数値
- リスク要因と対策
例えば、「今年度の営業研修はROI 150%を達成。1人あたり10万円のコストで25万円の利益創出に成功したため、次年度は対象を20名から50名に拡大し、投資額500万円に対し利益貢献1,250万円を見込む」といった提案を行います。
また、過去の研修効果が低かった領域については、改善策とともに再投資の必要性を説明することで、より戦略的な人材育成が実現します。このようにROIを活用した計画立案により、継続的な予算確保と組織力強化の好循環が生まれます。
CLF PARTNERSなら、研修ROIまで設計・算出して提案
CLF PARTNERSは、単なる研修提供にとどまらず、研修ROIの設計から算出、効果測定までを一貫してサポートする営業支援カンパニーです。
累計350社以上、3,000人以上の営業パーソンを支援してきた実績と、半年以上の継続率96.5%という数字が、当社の研修効果を証明しています。
当社の強みは、営業戦略から実行、仕組化、組織改善まで一貫して対応できる少数精鋭のプロフェッショナル集団であることです。
50以上の研修メニューから貴社の課題に合わせて最適なプログラムをカスタマイズし、新人営業研修、営業マネジメント研修、ソリューション営業研修など、レベルや目的に応じた研修を提供します。
さらに、研修後のフォローアップと効果測定により、ROI算出のサポートも実施。稟議書作成の支援や経営層への報告資料の作成も行い、研修投資の価値を可視化します。
「研修効果が見えない」「ROIをどう測ればいいか分からない」とお悩みの方は、ぜひCLF PARTNERSにご相談ください
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
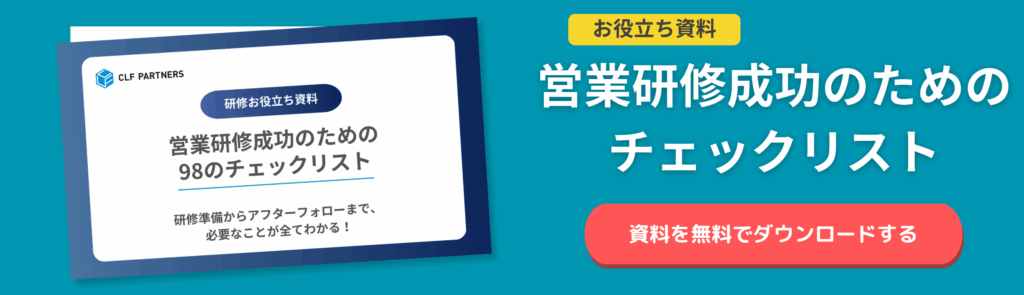
まとめ
研修ROIの算出は、経営層への説得材料として不可欠です。本記事では、ROI算出が必要な理由から、カークパトリックの4段階評価やフィリップスROIモデルといった具体的な考え方、さらに5つのステップでROIを計算する実践的な方法まで解説しました。
重要なのは、研修を「コスト」ではなく「投資」として捉え、レベル3(行動変容)を主軸に据えながら、ROI試算を参考値として提示することです。また、算出したROIは現場と経営層の両方にフィードバックし、成功要因を分析して再現可能な仕組みに落とし込むことで、組織全体の営業力向上につながります。
研修効果の可視化と次年度予算の確保でお悩みの方は、累計350社以上の支援実績を持つCLF PARTNERSにぜひご相談ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
この記事の監修者
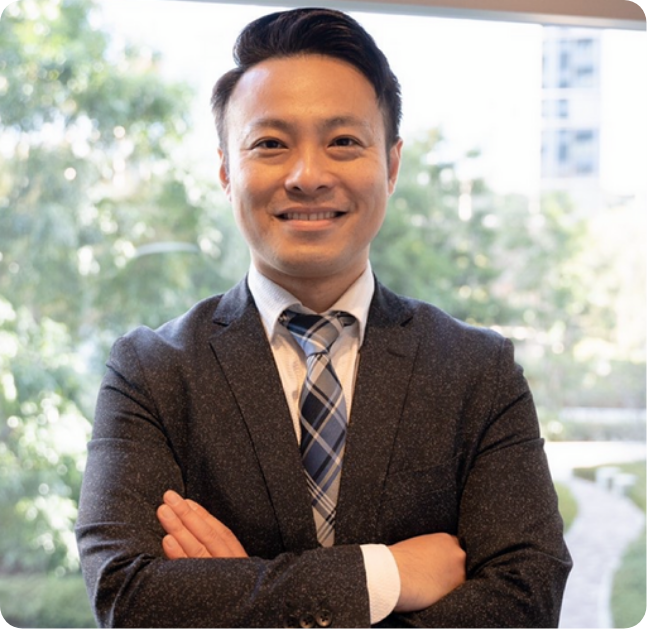
CLF PARTNERS株式会社
代表取締役社長 松下 和誉
大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事
公式Xアカウント:https://x.com/clf_km