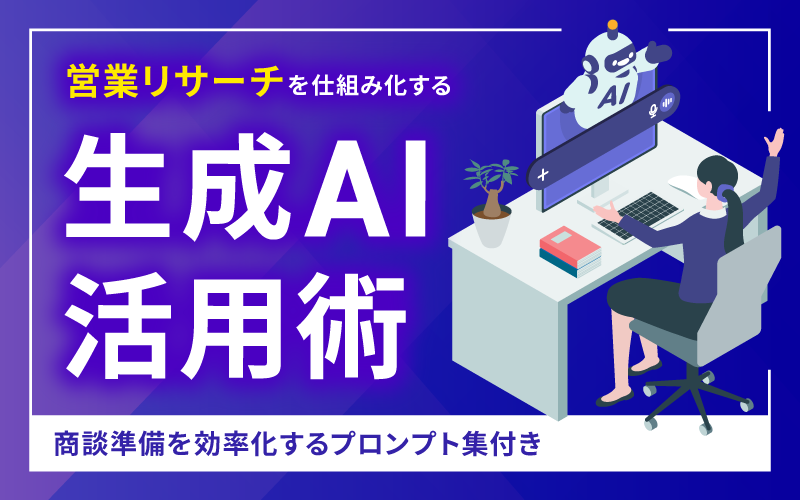営業研修・教育

「新人営業に教える時間が取れず、結局OJTという名のほったらかしになっている」
「商談に同席させているだけで、具体的に何を教えればいいかわからない」
「新人が『やることがない』と言い出し、早期離職につながっている」
こうした悩みを抱えるBtoB営業組織の管理職が増えています。
現場の営業メンバーは日々の目標達成に追われ、新人教育に手が回らないのが実情です。「OJTで育てる」と言いつつ、実際には商談に同席させるだけで終わっており、体系だった指導が行われていないケースがほとんど。
結果として、新人は「何をすればいいかわからない」状態に陥り、モチベーションを失って離職してしまう。そんな負のスパイラルに苦しむ組織も少なくありません。
「とりあえずOJTで」という場当たり的な対応では、持続可能な営業組織は築けません。今こそ、新人を「ほったらかし」にしない仕組みづくりが必要です。
本記事では、以下の視点から新人営業の育成課題とその解決策を解説します。
- 新人営業が「ほったらかし」になる3つの理由
- 放置することで起こる深刻なリスク
- ほったらかしを防ぐ具体的な対策
- 多忙な組織こそ外部研修を活用すべき3つの理由
CLF PARTNERSでは、忙しい営業組織でも実践できる新人育成の仕組みづくりを支援しています。体系的な研修プログラムにより、短期間で新人を戦力化し、育成担当者の負担を軽減。組織全体の営業力を底上げします。
- 現場が忙しく、新人教育に手が回らない
- OJTという名の放置から脱却し、体系的な育成制度をつくりたい
- 新人の早期離職を防ぎ、安定した営業組織を目指したい
そんな課題をお持ちの営業管理職の方は、ぜひ当社の営業研修プログラムをご検討ください。
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
営業人材育成をより効果的に進めたい方は、『新人営業向け営業人材育成にも活用できる 顧客開拓スキル完全ガイド』も併せてご活用ください。実践的かつ網羅的にスキルをまとめています。
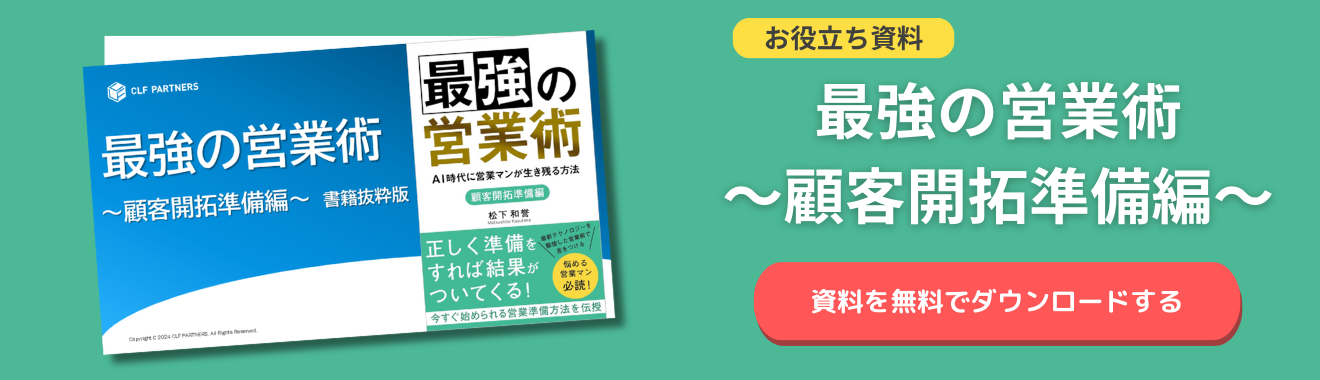
目次
なぜ新人営業は「ほったらかし」になるのか?3つの理由
新人営業が放置される状況は、決して上司や先輩の怠慢ではありません。日々の目標達成に追われる現場では、新人育成に十分な時間やリソースを割けないのが現実です。
この問題の背景には、主に3つの要因が複雑に絡み合っています。
育成担当者が多忙でリソースを割けない
新人営業が放置される最大の理由は、育成担当者が目の前の数字に追われ、教育に手が回らないことです。
実際、急成長企業への調査では、「新人教育ができていない」と答えた企業が53.3%と最多を占めています。さらに、72.1%の企業が営業組織の運営に「深刻な課題を感じている」と回答しており、「新人教育」や「業務プロセスの体系化」が喫緊の課題とされています。
また、「マネージャーの業務負荷が高い」との回答も40.0%に上り、管理職も手一杯である現状が明らかです。
このように、育成担当者の多忙さが新人教育の停滞を招いています。教育体制を組織的に再構築しない限り、この問題は根本的に解決できません。
参考:PR TIMES
体系的な教育カリキュラムが未整備
新人営業が「ほったらかし」にされる根本的な原因の一つは、組織に体系的な教育カリキュラムが存在しないことです。多くの企業では「OJT」の名のもと、明確な指導計画がないまま、属人的な育成に頼っています。
教育の基準がないため、何を・どの順番で・どう教えるかが指導者ごとに異なり、新人は混乱します。ある上司は商談スキルを重視し、別のマネージャーは関係構築を優先するなど、指導に一貫性がありません。その結果、新人は「何をすべきか分からない」状態に陥ってしまいます。
こうした属人的な育成は、特定の上司への依存を招き、営業スキルの組織内共有を妨げる要因にもなります。結果として、新人の自立が遅れ、負の循環が続くのです。
「OJT=商談同席」という誤解
新人営業が放置される3つ目の理由は、「OJT=商談同席」という誤解です。多くの企業では、同席させるだけで育成が完了したと思い込みがちですが、それだけでは学びにはつながりません。
背景となる意図や判断の根拠が共有されず、さらに商談後のフィードバックもないケースが大半です。これでは新人は良し悪しの判断ができず、成長の機会を逃してしまいます。
たとえ商談を何度見ても、事前準備や状況判断の力は養われません。重要なのは、同席後に感じたことを言語化し、「次はどうするか」を考えさせるフィードバックの場です。
つまり、「同席=OJT」という誤った認識が、新人の放置を招いているのです。
新人営業をほったらかしすることで起こる深刻なリスク
放置された新人は「やることがない」という停滞感に陥り、営業は辛い仕事だと感じやすくなります。モチベーションの低下や早期離職につながるだけでなく、戦力化の遅れや採用ブランドの低下といった組織的なダメージも招きます。ここからは具体的なリスクを整理していきます。
「やることがない」状態によるモチベーションの低下と早期離職
新人営業を放置する最大のリスクは、モチベーションの低下による早期離職です。明確な指示や目標がないままでは、自分の役割を見失い、組織への帰属意識も薄れていきます。
実際、育成で最も苦労している点として「新入社員のメンタルやモチベーション管理」(26.1%)が挙げられており、多くの育成担当者が心理的ケアに頭を悩ませています。特に深刻なのは、新人が「営業は辛い」と感じるようになるケースです。
やるべきことが曖昧なまま商談に同席しても、何を学ぶべきか分からず、時間だけが過ぎていくことに強いストレスを感じます。
例えば、以下のような状況では離職リスクが一気に高まります。
- 配属後1か月経っても具体的な業務指示がない
- 先輩の商談を見学するだけで、自分の役割が見えない
- 質問しても「まずは見て覚えて」としか言われない
- 日報を書いてもフィードバックが返ってこない
このような環境では、「この会社では成長できない」と判断し、入社半年以内に離職を決意する新人も少なくありません。離職は採用コストの損失だけでなく、残されたメンバーの負担増にも直結する深刻な問題です。
参考:「職場における新入社員育成の実態調査」の結果を発表|リクルートマネジメントソリューションズ
独り立ちできず、戦力化が遅れる
新人営業の放置は、個人の離職だけでなく、組織全体の戦力化を遅らせる深刻なリスクを招きます。OJTという名目で具体的な指導がないまま放置された新人は、いつまで経っても自力で売上を立てられるようになりません。
その結果、本来独り立ちすべき時期が大幅に遅れ、育成担当者やチームメンバーの負担は増え続けます。
例えば、新人への指導に費やすべき時間を確保できず放置した結果、以下のような悪循環に陥ります。
- 新人がいつまでも単独で商談を進められない
- 上司が常に新人のフォローに時間を割かれ、自身の業務が圧迫される
- 組織全体の生産性が低下し、チーム目標の達成が困難になる
新人一人を戦力化できないことは、単なる機会損失ではなく、組織全体の成長を鈍化させる根本的な要因となります。
特に、新規営業が重要な組織にとって、次世代の担い手が育たないことは、将来の事業成長を危うくする大きなリスクです。
組織文化の悪化と採用ブランドの毀損
新人営業の放置は、組織の内部だけでなく、外部にも悪影響を及ぼします。放置された新人は、退職後、口コミサイトなどにネガティブな体験を投稿する可能性が高まります。
具体的な例としては、以下のような口コミが挙げられます。
- 「入社後、何も教えてもらえず放置された」
- 「先輩は忙しそうで質問しづらい雰囲気だった」
- 「教育体制が全くなく、独学でやるしかなかった」
こうした低評価の口コミは、潜在的な求職者に大きな影響を与えます。優秀な人材ほど、入社後のキャリアや成長環境を重視するため、ネガティブな情報を見て応募をためらう可能性が高まります。
結果として、採用市場での競争力が低下し、優秀な人材が集まらないという負のスパイラルに陥ります。
営業新人をほったらかしにしないための具体的な対策
負のスパイラルを断ち切るには、属人的なOJTから脱却し、育成の仕組みを整えることが重要です。教育カリキュラムの導入や担当者の役割明確化、チーム全体での支援体制づくりが有効な手段となります。次に、実践的に取り入れたい対策について解説します。
教育カリキュラムを整備する
新人営業を「ほったらかし」にしない最も効果的な対策は、体系的な教育カリキュラムの整備です。属人的なOJTに頼るのではなく、誰が教えても一定の成果が出る仕組みを構築することで、育成の質を安定させることができます。
教育カリキュラムがあれば、新人は「何を、いつまでに、どのレベルまで習得すべきか」が明確になり、自分の現在地と目標を把握できます。これにより、「何をすればいいかわからない」という不安が解消され、成長に向けた行動が取りやすくなります。
例えば、次のような段階的なカリキュラムが有効です。
| 月数 | 学習内容 | 実践参加内容 |
|---|---|---|
| 1か月目 | – 業界・自社・商品知識習得 – 営業ツール操作(CRM/SFA) – 営業プロセス座学 | – 商談オブザーバー(第2週~) – ロープレで自己紹介やアイスブレイク練習 |
| 2か月目 | – トークスクリプト作成(挨拶・ヒアリング) – ケーススタディによる顧客課題整理 | – 商談で一部担当(挨拶・自己紹介) – 議事録作成・CRM入力 – 提案書の一部作成(フォーマット利用) |
| 3か月目 | – 提案書の一部(価格表・事例など)作成 – ヒアリング質問リスト作成 | – 小規模案件の部分担当(提案内容の説明) – 提案資料を使って発表 – クロージングは先輩がフォロー |
| 4か月目 | – 提案書を一人で仕上げる – 商談リハーサル(全体フロー) | – 小規模案件の単独担当(上司が同席) – 大規模案件は部分担当またはオブザーバー |
| 5か月目 | – フィードバックをもとに改善 – クロージング手法習得 | – 商談の大部分を担当(ヒアリング~提案) – クロージングの一部も挑戦 |
| 6か月目以降 | – 自立営業スキルの強化 – 複数案件の同時進行管理 | – 小規模案件は単独完結 – 大規模案件でサブリーダー役 – 新人へのOJT補助も経験 |
このようにステップを踏むことで、新人は自信を持って次のフェーズに進むことができます。
OJT担当者の育成スキル向上と役割を明確化する
新人の放置を防ぐには、OJT担当者の育成スキルを高め、その役割を明確にすることが欠かせません。担当者自身が「何をどう教えるべきか」を理解していなければ、体系的な育成は成り立ちません。
実際、満足度の高い育成方法として「OJT」(80.4%)が最多である一方、多くの担当者が十分な研修を受けないまま指導を任されている現状があります。
OJTは適切に実施すれば高い効果が期待できますが、担当者のスキル不足によって形骸化してしまうリスクもあります。
以下のような施策が、担当者の育成力向上に有効です。
- OJT担当者向けの事前研修の実施
- 育成計画やフィードバック手法の習得
- 担当者同士の定期的な情報共有会の開催
- 上司による継続的なサポート体制の整備
例えば、新人が3か月後に到達すべきレベルを定め、週次・月次で育成計画を立てることで、場当たり的な指導から脱却できます。
参考:【新人研修】満足度高いカリキュラムは「OJT」で8割、“実践型カリキュラム”が人気か。新入社員が満足/不満だった点は?|HRプロ
チーム全体で新人を育成する仕組みを作る
新人営業を「放置」しないためには、特定のOJT担当者に育成を一任するのではなく、チーム全体で新人を育てる仕組みを整えることが重要です。そうすることで、新人育成を組織全体の責務として捉えられ、属人化のリスクを避けられます。
一人の担当者だけでは、知識やスキルを網羅的に教えるのは難しく、負担も偏ります。チーム全体で関与すれば、新人は多様な視点から学び、多角的なスキルを効率的に身につけられます。
具体的には、以下のような仕組みが考えられます。
- ナレッジ共有会:成功事例やノウハウを定期的に共有し、新人も参加できる場を設ける
- メンター制度:OJT担当者とは別に、キャリアや悩みを相談できる先輩社員を配置する
- ペアセールス:案件ごとに複数の先輩と組み、異なる商談スタイルを経験させる
これらの取り組みは、新人の成長を加速させると同時に、チーム内のコミュニケーションを促進し、連携を強める効果も期待できます。
商談同席からロールプレイ形式へ発展させる
新人を「放置」しないためには、商談同席を単なる見学に終わらせず、事前準備と振り返りを徹底し、その流れの中でロールプレイを取り入れることが大切です。段階的に実践を積むことで、新人は実務で使えるスキルを着実に身につけられます。
この方法が効果的なのは、新人研修の実施率が約6割ある一方で、ロールプレイの導入率は42.9%にとどまっており、実践的な訓練が不足しているからです。商談同席だけでは受け身になりやすいですが、準備・振り返り・ロールプレイを組み合わせれば、能動的な学びにつながります。
効果的な流れの一例は以下の通りです。
| タイミング | 指導内容・流れ |
|---|---|
| 商談前 | 顧客情報を共有し、想定質問を確認 |
| 商談同席 | 新人に観察すべきポイントを明示 |
| 商談後 | 30分以内に振り返りを行い、気づきを言語化 |
| 翌日 | 学んだ内容をロールプレイで実践 |
例えば、同席した商談で先輩の提案手法を翌日のロールプレイで再現すれば、見て学んだ内容が「使えるスキル」として定着します。特に初期段階では、TOP営業の商談を丸ごとマネすることが重要です。
提案内容・言い回し・空気感まで忠実に再現することで、成果を出すための型が身体に染み込みます。そのうえで徐々に自分なりのアレンジを加えていくと、応用力が磨かれます
参考:PR TIMES
外部研修・コンサルティングを活用する
新人を「ほったらかし」にしないための有効な手段の一つが、外部研修やコンサルティングの活用です。社内に十分なリソースや専門知識がなくても、外部の力を借りれば短期間で体系的な育成体制を整えることができます。
外部活用が効果的なのは、自社内では気づきにくい課題を客観的に診断でき、さらに他社の成功事例を基にした実践的な解決策を提示してもらえるからです。
特に、育成担当者が多忙で十分な時間を割けない場合や、育成ノウハウが属人化している場合には、外部専門家の関与が大きな転機となります。
具体的なメリットには、以下のようなものがあります。
- 体系的な育成カリキュラムを短期間で導入できる
- 業界特有の営業手法を学べる実践型研修を受けられる
- 研修後も現場での伴走支援を受けられる
- 育成担当者の負担を大幅に軽減できる
「リソース不足で手が回らない」「育成の進め方がわからない」といった課題を抱える場合、外部専門家を頼るのも有効な選択肢です。
CLF PARTNERSでは、貴社の現状を客観的に診断し、最適な改善策のヒントを得られる
営業組織の課題と対策を60分無料で壁打ちを実施しています。
多忙な組織こそ「外部研修」を活用すべき3つの理由
現場が忙しいからこそ、新人育成を外部研修に委ねるメリットがあります。体系的な研修により教育を仕組み化でき、短期間での即戦力化も可能です。
さらに管理職は数字管理や戦略に集中できるため、組織全体の成果につながります。では、外部研修の具体的な効果を見ていきましょう。
教育を仕組み化することで指導負担を軽減できる
多忙な組織が外部研修を活用すべき最大の理由は、教育プロセスを仕組み化し、育成担当者の負担を大幅に軽減できる点です。
社内でゼロから育成体制をつくるには膨大な時間と労力がかかりますが、外部研修を導入すれば完成度の高いプログラムをそのまま利用できます。
その結果、担当者は「教材づくり」ではなく「新人がどこでつまずいているか」「どうすれば成長を促せるか」といった本質的なサポートに専念できるようになります。
さらに、指導内容が標準化されるため、誰が指導しても一貫性のある学習機会を新人に提供でき、育成コストの削減と生産性向上につながるでしょう。
専門的な研修で短期間に即戦力化できる
外部研修は、新人営業を短期間で即戦力に育成する上で非常に効果的です。
外部の研修プログラムは、業界の最新トレンドや実践的なノウハウが凝縮された専門性の高い内容だからです。自社内では教えきれない実践的なスキルや、営業の「型」を効率的に学べます。
例えば、以下のような実践的なトレーニングを外部講師から直接受けることで、新人は実際の業務で通用するスキルを短期間で習得できます。
- 徹底したロールプレイング
- 顧客心理に基づいた商談の進め方
- 最新の営業ツールを活用した効率化ノウハウ
これにより、新人が独り立ちするまでの期間を大幅に短縮でき、早期から組織の売上に貢献できるようになります。
上司は「数字管理」と「戦略」に集中できる
外部研修を活用することで、営業部のマネージャーや部長クラスは、新人教育から解放され、本来注力すべき業務に集中できるようになります。新人育成の多くを外部に委ねることで、上司は以下の重要な業務に時間を使えるようになります。
- チーム全体の数字管理と進捗管理
- 市場分析に基づいた営業戦略の策定
- 既存メンバーのスキルアップ支援やモチベーション管理
特に、急速に変化する市場において、営業戦略の立案や見直しは、組織の成長を左右する最重要タスクです。
新人育成というタスクから解放されることで、上司は全体を俯瞰し、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、組織全体の生産性向上に直結し、持続的な事業成長を可能にするでしょう。
CLF PARTNERSの営業新人向け基礎研修プログラム
CLF PARTNERSでは、新人営業が抱える「ほったらかし」の課題を解決するため、実践的な新人営業向け基礎研修プログラムを提供しています。本プログラムは、座学と実践をバランスよく組み合わせることで、新人が短期間で即戦力となるためのスキルと自信を身につけることを目指します。
この研修では、営業の基礎概念から始まり、顧客視点に立った提案方法、さらに貴社の業界・商材に特化したケーススタディやロールプレイを通じて、現場で通用する実践力を徹底的に磨き上げます。
CLF PARTNERSの営業新人向け基礎研修プログラムについて、さらに詳しい内容や具体的なカリキュラムにご興味がある方は、以下のリンクよりサービス資料をご覧ください。
⇒CLF PARTNERS 新人営業研修「Basic Sales Training」
新人育成に関するお役立ち情報も掲載しています。
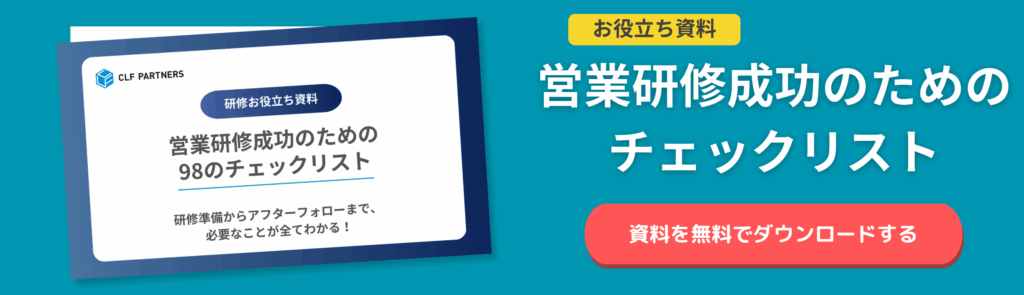
まとめ
新人営業が「ほったらかし」にされる背景には、育成担当者の多忙さ、体系的なカリキュラムの欠如、そして「OJT=商談同席」という誤解があります。放置すれば、早期離職や戦力化の遅れ、採用ブランドの毀損といった深刻なリスクを招きます。
解決策として、教育カリキュラムの整備、OJT担当者のスキル向上、チーム全体での育成、商談同席とロールプレイの連動、そして外部研修の活用が有効です。特に多忙な組織では、外部研修により教育を仕組み化し、短期間で即戦力化を実現できます。
CLF PARTNERSでは、累計350社、3,000人以上を支援した実績をもとに、新人を短期間で即戦力化する体系的な研修プログラムを提供しています。
新人を「ほったらかし」にしない組織づくりは、今日から始められます。まずは貴社の現状を診断し、最適な改善策を見つけることから始めませんか。
⇒新人営業研修プログラムの詳細を見る
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
この記事の監修者
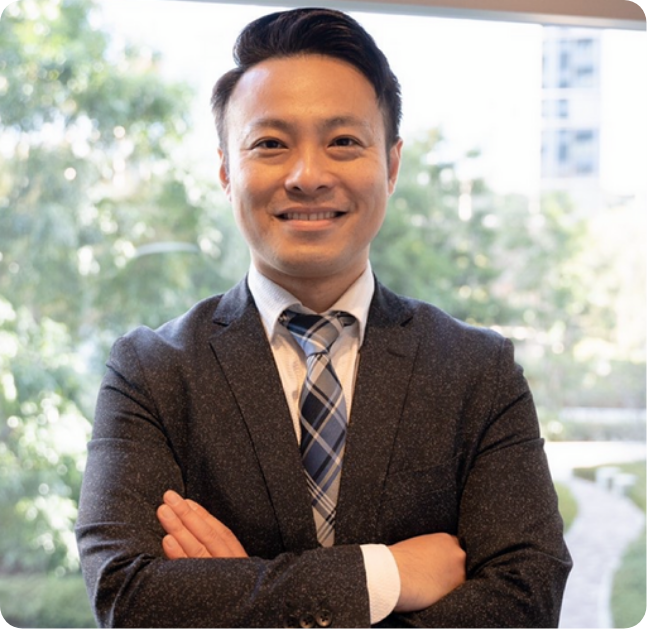
CLF PARTNERS株式会社
代表取締役社長 松下 和誉
大学卒業後、大手総合系コンサルティングファームに入社。最年少で営業マネジャーに就任。中小企業から大手企業まで幅広くコンサルティング業務を実施。また、文部科学省からの依頼を受け、再生機構と共に地方の学校再生業務にも従事。 その後、米Digital Equipment Corporation(現ヒューレットパッカード)の教育部門がスピンアウトした世界9ヵ国展開企業のJAPAN営業部長代行として国内の最高売上に貢献。 現在は関連会社12社の経営参画と支援を中心に、グループの軸となるCLF PARTNERS㈱ではVC出資ベンチャー企業、大企業の新規事業の支援に従事
公式Xアカウント:https://x.com/clf_km